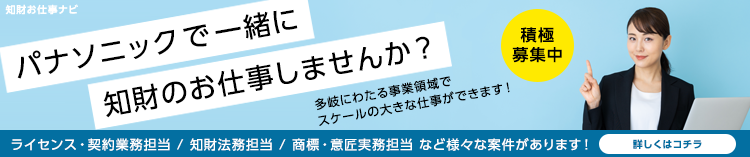| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|
| 事件 |
平成
16年
(ワ)
11546号
損害賠償等請求事件
|
|---|---|
|
原 告有限会社日本システム設計 訴訟代理人弁護 士後藤真孝 同 後藤美穂 被 告株式会社ケル・システム 訴訟代理人弁護 士室谷和彦 |
|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 2007/07/26 |
| 権利種別 | その他 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
1被告は,グラブ浚渫施工管理プログラム G1Xver3.00,同 ver5.24,同ver5.40,同 ver5.50,同 ver5.60,同 ver5.70 を複製,販売してはならない。 2被告は,原告に対し,700万円及びこれに対する平成16年11月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3被告は,原告に対し,257万5000円及びこれに対する平成16年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4原告のその余の請求を棄却する。 5訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。 6この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
全容
第1請求1主文第1項,第3項に同旨2被告は,原告に対し,1013万2005円及びこれに対する平成16年11月11日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2事案の概要本件は,原告が,被告に対し,①主位的に,グラブ浚渫施工管理システムに関するプログラムを作成した者から,そのプログラムの著作権を譲り受けたとして,同プログラムの著作権に基づき著作権法112条1項により,予備的に,上記プログラム作成者・被告間の上記プログラムの複製販売の許諾契約に基づき,プログラムの複製,販売の差止めを求め,②主位的に,上記プログラム作成者から債権譲渡された上記プログラムの著作権侵害による損害賠償を求め,予備的に,上記複製販売許諾契約に基づき,上記プログラム作成者から債権譲渡された上記プログラムの複製,販売の許諾料の支払を求め,③別のソフトについて,原告・被告間のソフトの開発ないし改造等の請負契約に基づき,未払代金の支払を求めた事案である。 第3前提となる事実(証拠により認定した事実は末尾に証拠を掲げた。証拠の枝番は省略することがある。)1当事者等(1)原告原告は,主としてコンピュータソフトの開発,販売,リース等を業とする会社で,代表取締役はA(以下「A」という。)であり,平成15年6月26日に設立された。原告が設立される以前は,Aが個人で「日本システム設計」という屋号でコンピュータソフトの開発等を行っていた。 (2)被告被告は,業務用ナビゲーションシステムの開発,製造,販売,リース等を業とする会社で,現在の代表取締役はB(以下「B」という。)であり,平成12年8月16日に有限会社として設立された後,株式会社となった。 (3)株式会社橘高工学研究所(以下「橘高工学」という。)橘高工学は,業務用ナビゲーションシステムの開発,製造,販売,リース等を業とし,Bが代表取締役を務める会社であった。 橘高工学は,平成12年5月22日に1回目の不渡りを出し,同月25日に2回目の不渡りを出して,同年6月15日午後0時,大阪地方裁判所において破産宣告を受けた。(不渡りを出した日付については乙54)なお,Bも,同年7月6日午前10時50分,奈良地方裁判所葛城支部において破産宣告を受けた。 2船体位置決めシステム及びグラブ浚渫施工管理システムの開発経過(1)船体位置決めシステム(LAH シリーズ・LAH-Ⅱ等)の開発ア船体位置決めシステムの内容橘高工学と国土総合建設株式会社(以下「国土総合建設」という。)は,昭和61年ころから平成元年ころにかけて,「自動追尾方式の光波距離計測装置」及び「船台位置決め方法」に関する技術を開発し,同技術に係る発明について4件の特許出願をした。(乙12ないし14,21)当時の船体位置決めシステムは,上記の「自動追尾方式の光波距離計測装置」及び「船台位置決め方法」に関する技術を用いて,作業船の位置(座標等の数値で表される。)を測定,算出するシステムであった。その方法は,まず,作業船に設置された光波距離計測装置における2台の自動追尾光波距離計を用いて,船体の位置を計算するのに必要な距離や水平角のデータを求め,次に,同各データが作業船内のコンピュータに送付され,「船台位置決め方法」により,上記の送付されたデータを作業船内のコンピュータで位置演算処理をして,船体位置を計算するものであった。各データと演算処理された結果は,それぞれ座標の数字及び座標上の位置図として,作業船内のコンピュータの画面ディスプレイに表示された。(乙54)イ船体位置決めシステムに関するプログラム(ア)船体位置決めプログラム N88 BASIC 版Aは,橘高工学から依頼を受けて,昭和63年10月20日ころ,船体位置決めシステムのアプリケーションソフト(マンマシンソフト)である(甲15はその画面のハード船体位置決めプログラム ver1.0 N88 BASIC 版コピーの一部,甲25はそのソースプログラム。以下「位置決めプログラム NB 版」という。)を作成した。同プログラムは,自動追尾光波距離計測装置から送信されたデータによる位置演算処理,作業環境の設定,船体位置を数値及び図で表示するものであった。(乙22,54)(イ)橘高工学におけるプログラムの追加変更橘高工学従業員C(以下「C」という。)は,昭和63年11月以降,位置決めプログラム NB 版に数回にわたり追加変更を加えた(ver1.5,ver1.5b,ver1.6。)。同追加変更にAは関与していない。(乙23,24,31の2)(ウ)船体位置決めプログラム Quick BASIC 版Cは,平成元年5月ころ,位置決めプログラム NB 版について,その言語を N88 BASIC から Quick BASIC に書き換え,内容の一部を修正する作業を行い, (LAH-ver2.0 以降。乙船体位置決めプログラム Quick BASIC 版23はその画面のハードコピー,乙24はそのソースプログラムの一部。 以下「位置決めプログラム QB 版」といい,位置決めプログラム NB 版と併せて「位置決めプログラム」という。)を作成した。同プログラムの作成にAは関与していない。(原告代表者8ページ,乙31の2)ウ船体位置決めシステムの納品橘高工学は,平成元年4月,位置決めプログラム NB 版(ただしCが変更を加えた後のもの)を搭載した船体位置決めシステム(光波測距システム1号機・LAH シリーズ)を国土総合建設に納品し,同年6月,位置決めプログラム QB 版がインストールされた船体位置決めシステム(LAH シリーズ)を大石建設に納品した。(乙32,54)なお,船体位置決めシステムは,そのプログラム部分も含めて,平成2年6月29日に運輸大臣(当時)による評価証を受けている。(乙22)エ著作物性位置決めプログラムは著作物である。(争いがない)(2)グラブ浚渫施工管理システムの開発(LAH シリーズ・LAH-V 等)アグラブ浚渫施工管理システムの内容平成2年に開発されたグラブ浚渫施工管理システムは,グラブ浚渫船の船体位置決めと堀跡管理の機能を有するものであった。 グラブ浚渫船は,グラブバケットによって水底土砂をつかみ揚げ,自船の泥倉又は舷側に接舷した土運船に積載する浚渫作業船である(乙16)。堀跡管理機能とは,浚渫船が行った作業(水底土砂の掘削)の状況(位置,範囲,深さ等)を正確に把握して作業状況を管理する機能である。 当時のグラブ浚渫施工管理システムに組み込まれていた船体位置決めシステムは,従来の船体位置決めシステムにあった2台の自動追尾光波距離計によるデータ収集に加え,重機に備え付けられた旋回角計,ジブ角計,深度計のセンサーからのデータの取込みが可能となり,あらかじめ入力された船体の寸法に基づいて演算処理をして,船体の位置情報及びグラブバケットの位置情報を計算し,これらを画面ディスプレイにリアルタイムで表示するものであった。 当時のグラブ浚渫施工管理システムのうちの堀跡管理システムは,上記の船体位置決めシステムに,潮位データ等を取込み,堀跡指示用データ入力装置を付加して堀跡の演算処理を行い,画面ディスプレイに平面図での1工区ごとの浚渫堀跡深さ等(工区データ,仕掛りデータ,出来高データ等)を表示するものであった。(乙17)なお,平成3年に,重機に関する情報(旋回角,ジブ角,深度)について,重機に取り付けたセンサーからデータ送信されていたものが,シリアル通信(RS232c)により信号として重機から直接受けることができるようになった。 (乙54)イグラブ浚渫施工管理システムに関するプログラム橘高工学は,Aにグラブ浚渫施工管理システムに関するプログラムの作成グラブ浚渫施工管理プログラム を発注し,Aは,平成2年11月ころ,(甲17〔LAH-Vver1.0,平成2年11月ころのバ ver1.00 MS-DOS C 言語版ージョン〕,甲18〔LAH-Vver2.0,平成3年1月ころのバージョン〕はいずれもその画面のハードコピーの一部。後述するとおり,システムを設置する作業船によってプログラムの名称は異なるが,以下「GDX 等」という。)を完成させた。 ウグラブ浚渫施工管理システムの納品橘高工学は,平成2年11月,GDX 等がインストールされたグラブ浚渫施工管理システム(LAH-V)を青木組に納品した。(乙32)(3)GPS 装置付きグラブ浚渫施工管理システム(NAV-LAH シリーズ)の開発アGPS 装置付きグラブ浚渫施工管理システムの内容平成8年,位置決め機能に GPS 装置が追加され,船体位置決めの方法は,自動追尾光波距離計と GPS 装置のいずれかを選択できるようになった。GPS装置は,GPS 受信ボードと CPU 演算装置を用いてリアル・タイム・キネマティック(RTK)演算を行い,アンテナの位置をX,Y座標で表現し,シリアル通信(RS232c)により出力するものであった。 イGPS 装置付きグラブ浚渫施工管理システムに関するプログラム(GNX 及びG1X シリーズ MS-DOS C 言語版)(ア)Aは,平成8年8月ころ,橘高工学の依頼を受けて,GPS 装置からのGPS 対応グラブ浚渫施工管理プログラム GNX MS-DOS 通信処理を追加したを作成した(以下「GNX」という。当初の名称は GNX であり,平 C 言語版成9年5月以降は G1X シリーズ〔初期バージョンは G1Xver1.1〕とされた。 甲14,44)。 (イ)GPS 処理(入力部分,演算部分,出力部分)のうちの演算部分は,「RtGps3.dll」という名前のダイナミック・リンケージ・ライブラリ(DLL,動的リンク専用のライブラリ)を始めとする WayPoint 社が作成した GPS 処理システムソフトのプログラムないしモジュールが用いられていた。(甲10,12,乙7)GPS 対応グラブ浚渫施工管理 (ウ)Aは,平成9年5月,喫水計を追加した(以下「G1Xver1.20」という。) プログラム G1Xver1.20 MS-DOS C 言語版GPS 対応グラブ浚渫施工管理プログラム を完成させ,平成11年5月,(乙46の1はそのソースプログラム。以下 G1Xver2.00 MS-DOS C 言語版「G1Xver2.00」といい,他の G1X についても同様にバージョン名でいう。 また,GDX 等,GNX,G1Xver1.1 から G1Xver2.00 までを併せて「G1X MS-DOS版」という。)にバージョンアップした。上記の各プログラムは,マルチタスク・リアルタイム・モニター(乙46の2は G1Xver2.00 に使用されている RTM のソースプログラムの一部〔ヘッダーファイル「rtm.h」。以下「RTM」という。〕。原告代表者25ページ)のもとで作動するものであった。 (エ)RTM は,Aが平成5年に独自に開発した一種のOSであり,そのプログラムの著作権はAに帰属する(争いがない)。 ウシステムの納品橘高工学は,平成8年から平成11年まで,G1X MS-DOS 版をグラブ浚渫施工管理システム(NAV-LAH)にインストールして販売していた。 エ著作物性G1X MS-DOS 版は,位置決めプログラムを前提とするプログラムであるが,その創作性については,後述するとおり,争いがある。 (4)プログラムの開発(G1W Windows Visual Basic 版)Aは,平成10年ないし11年ころ,G1X MS-DOS 版を Windows 版に変更したGPS 対応グラブ浚渫施工管理プログラム G1W Windows Visual プログラムである(乙33はその画面の一部。以下「G1W」という。)を作成した(時 Basic 版期については被告代表者38,39ページ,甲40の52ページ,乙55の4,平成17年2月3日付け原告の第2回準備書面9ページ参照)。 同プログラムでは,GPS の演算処理と位置決めプログラムが別々の CPU で演算処理されていたものを組込型 CPU 装置を用いて1つの CPU で処理されるよう修正された。また,GPS の RTK 演算に新方式の GPAD(GPS Position andAzimuth Determination)演算を用いることとし,船体位置決め・堀跡管理の演算を一体とした。 G1W はソナー装置に対応するように開発されていなかった。ソナー装置は,超音波発信器と演算装置からなり,海底の形状を超音波の反射により解析する装置である。(弁論の全趣旨)(5)プログラムの開発(G1X Windows VisualC++版)アG1Xver3.00(Windows VisualC++版)(ア)Bは,平成12年1月,Aに対し,堀松建設工業株式会社(以下「堀松建設」という。)に納品する NAV-LAH Ⅲに用いるグラブ浚渫施工管理システムのプログラム(第16堀松号〔あるいは「第16堀松丸」。いずれの名称が正しいかは記録上不明であるため,本判決ではとりあえず「第16堀松号」という。〕に設置されている新型ソナー装置に対応するもの)の作成を発注した。 GPS 対応グラブ浚渫施工管理プログラム G1Xver3.00 Windows (イ)Aは,(甲36は平成12年7月時点でのソースプログラム,乙4 VisualC++版1,42はその画面の一部。乙50は同年4月時点での取扱説明書。G1Xの Windows VisualC++版の初期バージョンである。以下「G1Xver3.00」という。)を少なくとも同月ころまで作成し(完成の時期については争いがある。),G1Xver3.00 は,同月,第16堀松号に設置する NAV-LAH ⅢのGPS 受信演算装置にいったんインストールされ,同装置は第16堀松号に設置されたが,第16堀松号の NAV-LAH Ⅲのオプションであるソナー計測装置に不具合があり,調整が必要となった。(乙39,42ないし44)(ウ)同年6月,橘高工学が破産宣告を受けたため,Aは,重機メーカーである「四国建機SKK」(堀松建設のグラブ浚渫船の発注先であり,うちグラブ浚渫施工管理システム NAV-LAH Ⅲについては,橘高工学から日立造船等を介して四国建機SKKに納品されている。以下「SKK」という。)から依頼を受けて,G1Xver3.00 についてソナーに関する調整,潮位データの平均化の調整を行い,同年7月に同作業を終了した。Aは,SKKから開発費等として335万円の支払を受けた。(甲33)イG1Xver3.00 のバージョンアップAは,被告から,G1Xver3.00 のバージョンアップを依頼され,次の各プログラムを作成した(これらのプログラムの各バージョン情報画面は甲8のとおりである。以下,G1Xver3.0 に下記の各プログラムを併せて「本件プログラム」という。また,位置決めプログラム,G1X MS-DOS 版,G1W を併せて「本件前プログラム」という。)。本件プログラムは,いずれもバージョンによる細かな違いはあるものの,著作物としては同一のプログラムである。 GPS 対応グラブ浚渫施工管理プログラム G1X ver5.24 Windows (ア)(以下「G1Xver5.24」という。) VisualC++版GPS 対応グラブ浚渫施工管理プログラム G1X ver5.40 Windows (イ)(甲19はそのソースプログラムの一部〔G1xLan.cpp〕。以 VisualC++版下「G1Xver5.40」という。)G1Xver5.40 は,「現在の潮位データを DO ボードに転送させる。」ようにバージョンアップされている(甲13)。 GPS 対応グラブ浚渫施工管理プログラム G1X ver5.50 Windows (ウ)(甲20,乙18,乙47の1・2はそのソースプログラム VisualC++版の一部。以下「G1Xver5.50」という。)G1Xver5.50 は,「転船時,船体表示モードを追加」するようにバージョンアップされている(甲13)。平成15年2月ころから3月ころ,サハリンのホルムスク港において西村組のグラブ浚渫船に残されていたソースプログラムは同バージョンである。(甲13,22,44)GPS 対応グラブ浚渫施工管理プログラム G1X ver5.60 Windows (エ)(甲21はそのソースプログラムの一部〔G1xLan.cpp〕。以 VisualC++版下「G1Xver5.60」という。)G1Xver5.60 は,「GPS(Novatel RT2)タイプに対応」するようバージョンアップされている(甲13)。 GPS 対応 (オ)(以下 グラブ浚渫施工管理プログラム G1Xver5.70 Windows VisualC++版「G1Xver5.70」という。)G1Xver5.70 は,「ジブ角度計と旋回角度計のエンコーダーが異なるタイプに対応」,「ジブ角度系と旋回角度計のエンコーダーの12ビット,10ビットの2種類に対応」する機能を追加したもので,平成15年7月ころに修正された(甲13)。 ウ著作物性本件プログラムは,少なくとも G1X MS-DOS 版を前提とするプログラムであるが,その創作性については,後述するとおり,争いがある。 3金銭の授受(1)橘高工学は,受取人をAとして,次のとおり約束手形を振り出した(以下,下記表の一番左側の欄の丸数字により,例えば同欄①の手形を「本件手形①」のようにいい,これらを併せて「本件各手形」という。)。 振出日満期日額面手形番号証拠バック①H12.1.20H12.4.25170万円GE2607乙4049万円②H12.1.20H12.4.25200万円GE2608乙40200万円③H12.2.21H12.5.25250万円HB03314甲5の1 250万円④H12.2.21H12.5.25130万円HB03315甲5の2 100万円⑤H12.3.21H12.6.25150万円HB03378甲5の335万円⑥H12.4.20H12.7.25200万円HB03407甲5の4 100万円(2)本件各手形の手形金の支払ア「バック」について橘高工学のAに対する支払は,主として手形により行われていたが,橘高工学は,手形金の一部について,いわゆる「バック」ないし「キックバック」として,Aが割引を受けて受領した手形金について,Aから橘高工学に払い戻させていた。 イ本件各手形本件各手形については,前記(1)の表の「バック」欄記載の各金額について,Aは,橘高工学に対し,「バック」させられている。 ウ不渡り本件手形③ないし⑥は不渡りとなった。 4本件プログラムの複製販売被告は,本件プログラムについて20の複製をして,グラブ浚渫施工管理システムにインストールし,平成12年11月から平成16年3月まで,別紙1のとおり,取引先に販売し納品した。 5権利の譲渡等(1)橘高工学から被告への譲渡ア特許権及び什器備品等橘高工学の破産宣告後,被告は,橘高工学の破産管財人弁護士谷口由記から,橘高工学が有していた特許権,サーバ,什器備品を譲り受けた。同サーバ内には,G1X MS-DOS 版の一部のプログラムが保存されていた。(乙9,10,54,58)イ著作権橘高工学の破産宣告後,同社に帰属していた著作権が第三者に譲渡されたことはない。 (2)Aから原告への譲渡ア著作権Aは,遅くとも平成18年5月までに,本件プログラムの著作権(ただし,著作権の有無・帰属については争いがある。)を原告に譲渡した。(甲39の1)イ著作権侵害に基づく損害賠償債権Aは,遅くとも平成18年5月までに,上記4の本件プログラムの複製に関して,本件プログラムの著作権侵害による損害賠償債権(ただし,債権の存否については争いがある。)を原告に譲渡し,同年8月19日,上記の譲渡について被告に通知した。(甲39の1・2)ウ契約に基づく複製許諾料債権Aは,遅くとも平成18年5月までに,上記4の本件プログラムの複製に関し,契約に基づく複製許諾料債権(ただし,債権の存否については争いがある。)を原告に譲渡し,平成19年3月29日,上記の譲渡について被告に通知した。(甲48の1・2)6ソフト開発・改造契約に基づく請求に関する事実(1)ソフト開発・改造契約の成立(以下,次の各契約を併せて「本件ソフト開発・改造契約」という。)ア原告は,被告との間で,平成15年8月ころ,ポンプ浚渫ソフト PIX 一式を代金210万円で開発する契約をし,同月25日ころ,上記ソフト一式を完成させて被告に対して引き渡した。 イ原告は,被告との間で,平成15年10月ころ,福丸建設の G1X を代金31万5000円で改造する契約をし,同月10日ころ完成させて被告に引き渡した。 ウ原告は,被告との間で,平成15年12月ころ,吉田組の IPX バージョンアップと現地調整を代金115万5000円でする契約を締結し,同月31日ころ,バージョンアップを完成させて被告に引き渡し,現地調整を行った。 被告は,原告に対し,上記代金のうち110万円を支払った。 エ原告は,被告との間で,平成16年3月ころ,13福丸建設,大和(山陽)の GPAD(世界測地系)のソフト(GPADver4.0 及び GPADver4.1s。以下「本件 GPADver4 ソフト」という。)を代金10万5000円で開発する契約をし(以下「本件 GPADver4 開発契約」という。),同月20日ころ,被告に引き渡した。 (2)相殺1に関する事実ア被告は,平成14年5月ころ,Aに対し,森長組向けに,橘高工学時代に作成された斜杭打設管理システムのソフト(ver1.0,MS-DOS C 言語版。以下「本件斜杭打設管理ソフト」という。)の Windows VisualC++版を作成するよう依頼し(以下「本件斜杭打設管理ソフト変更契約」という。),Aは,外注費を受領して,本件斜杭打設管理ソフトの Windows VisualC++版を完成させた。(甲1の14,甲2の4,甲3)イ原告は,斜杭打設管理システムソフトを株式会社アムテックスを介して古野電気株式会社(以下「古野電気」という。)に納品し,古野電気は,同ソフトをインストールした斜杭打設管理システムを,平成15年11月30日,大旺造機に納品し,同システムは,中国籍の「寧波海力801」という船に設置された。 ウ被告は,平成19年4月24日の第3回口頭弁論期日において,原告の被告に対する本件ソフト開発・改造契約に基づく代金債権と被告の原告に対する後記第5の11(1)記載の損害賠償債権とを対当額で相殺する旨の意思表示をした。 (3)相殺2に関する事実ア原告は,平成16年5月ないし6月,被告の取引先25社に対し,別紙2の文書(乙5,6。以下,乙5の文書を「乙5文書」,乙6の文書を「乙6文書」といい,これらを併せて「本件送付文書」という。)をファックスないし内容証明郵便等により送付した。 イ被告は,平成19年4月24日の第3回口頭弁論期日において,原告の被告に対する本件ソフト開発・改造契約に基づく代金債権と被告の原告に対する後記第5の12(1)記載の損害賠償債権とを対当額で相殺する旨の意思表示をした。 第4争点1著作権に基づく請求(1)本件プログラムの創作性の有無(2)本件プログラムの著作権の帰属(3)G1X MS-DOS 版の創作性の有無(4)本件前プログラムの著作権の帰属(5)著作権の権利主張についての対抗要件の要否(6)著作権に基づく差止請求についての侵害のおそれの有無(7)著作権侵害についての被告の故意過失の有無(8)著作権侵害による損害発生の有無及びその数額2複製許諾契約に基づく請求本件プログラムについての複製許諾契約の有無3本件ソフト開発・改造契約に基づく請求(1)本件 GPADver4 開発契約に基づく代金の支払拒絶の可否(2)相殺1の成否(3)相殺2の成否第5争点に関する当事者の主張1本件プログラムの創作性の有無(前記第4の1(1)の争点)(1)原告の主張ア言語及び OS の変更本件プログラムは,G1XMS-DOS 版を前提としているが,OS も MS-DOS とWindows とで異なり,言語も C 言語と VisualC++とで異なるので,創作性がある。 イ機能の追加等次の機能が追加され,本件プログラムのソースプログラムのコーディング文字数を単純に比較しても,本件プログラムは,G1X MS-DOS 版の5倍以上に増加している(甲24)。 1)GPS データの取込みの選択G1X MS-DOS 版では,RTK により国家座標に変換する装置からの取込みは,RS232C 通信による外部からの取込みのみであったが,本件プログラムでは,それに加えて GPAD(GPS 処理システム)による取込みを選択できるようになった。 2)光波計システムと GPS システムの共用G1X MS-DOS 版では,光波計システムと GPS システムのいずれか1つしか使用できなかったが,本件プログラムでは,両システムの共用が可能となった。 3)RTM に相当する部分の関数G1X MS-DOS 版では,RTM(Windows 自体には対応していない。)がその機能を担っていたマンマシン・インターフェイスを担う関数を,本件プログラムで新たに構築する必要があり,これを構築した。 ウ新たに可能となった処理次の処理が,G1X MS-DOS 版では不可能又は困難であったが,本件プログラムでは可能となった。 ①マウス操作による施工実績データのエクセル等のシステムへの転送,統計等の資料作成G1X MS-DOS 版では,施工実績データの解析や統計等の処理をするのに別のソフトを組む必要があったが,本件プログラムでは,施工データ自体をそのままエクセルなどのシステムにコピーでき,エクセル等において施工実績データの解析や統計等の処理が可能である。これは Windows 上で動作していれば自動的に備わるものではなく,Windows 版の G1X に必要な API関数を作動させるようにプログラミングすることにより初めて可能となるものである。 ②ソナー装置のデータからの鳥瞰図の表示,施工実績データからの鳥瞰図の疑似的表示G1X MS-DOS 版では,データから鳥瞰図を表示することができなかったが,本件プログラムでは可能となった。鳥瞰図の態様は,創作者の個性が現れるものであり,いかなるプログラマーが作成しても乙48の23ページのようになるわけではない。 本件プログラムの鳥瞰図は,a)任意に設定した深度範囲の色テーブルで描画され,b)マウスを描画された鳥瞰図の任意の位置に移動させると,その位置のローカル座標と深度が表示され,堀残し位置が特定でき,c)魚礁設置等での活用や実際の施工運用で有能な機能があること等に特徴がある。 d)鳥瞰図のデザイン,大きさ,縮尺,色等もAが機能性や見やすさをふまえて独自に設定したものである。e)目標座標の設定,視点の位置(方位角,仰角,斜距離の要素),拡大縮小及び前記 b)は,鳥瞰図のプログラムであれば当然に付随するものではなく,Aが鳥瞰図のプログラムを有用にするために付けた機能である。f)最も特徴的であるのは,本件プログラムでは,ソナー装置がなくても,擬似的に鳥瞰図を作成できることである。 陰線処理等のプログラム設計はソフト技術者ごとに手法が異なるもので,難易度の高いソースを記述する必要にせまられる。一般化している機能であっても,難易度が高く,技術者ごとに手法が異なる処理プログラムの設計の場合は個々の技術者の個性が生かされるので創作性はある。 ③潮位データの印刷④カラー印刷での画面ハードコピーG1X MS-DOS 版では,カラー印刷はできなかったが,本件プログラムでは,カラー印刷をするためのプログラムを追加した。G1X MS-DOS 版のメイン画面のハードコピー印刷は,画面の背景色を濃紺で作成しているためそのままでは印刷が見づらいので,画面印刷時には,背景色等変更して印刷を見やすくしている。 ⑤現在の工区別施工データ件数の表示⑥操船室からの重機室のコンピュータ電源,システム再起動操作G1X MS-DOS 版では操船室から重機室のコンピュータの電源,システム再起動操作はできなかったが,本件プログラムでは可能となった。グラブ浚渫施工管理プログラムは,操船側と重機側がセットで使用されるもので通信回線でつながれているところ,コンピュータ操作は,通常操船側から重機側のコンピュータの電源も遠隔操作しなければならず,ソフトの入替も操船側から重機側に転送し再起動操作も可能である。 エまとめ本件プログラムは,上記のとおり,G1X MS-DOS 版とは異なる独自の創作性があり,本件前プログラム(主として G1X MS-DOS 版)とは同一の著作物ではない。 (2)被告の主張ア言語及び OS の変更(ア)本件プログラムに独自の創作性はなく G1Xver2.00 及び G1W を修正して作成したものにすぎず,実質的にはその複製である。G1W は G1X MS-DOS版を Windows 版にしたものにすぎないし,G1Xver3.00 は,G1W を前提に,G1Xver2.00 を MS-DOS C 言語版から Windows VisualC++版にしたものにすぎず,コーディングにある程度の時間はかかったとしても創作行為はない。 したがって,本件プログラムが(二次的)著作物となることはない。 (イ)原告は,本件プログラムは,G1XMS-DOS 版とは,OS が MS-DOS とWindows とで異なり,プログラム言語も C 言語と VisualC++とで異なるので,創作性が認められると主張する。 しかし,MS-DOS 対応 C 言語から Windows 対応 VisualC++言語への変更に必要となる作業は,Ⅰ)画面リソースの構築,Ⅱ)ボタン,メニュー,入力項目イベントの記述,Ⅲ)Windows でのグラフィック表現をするための手続追加,Ⅳ)文法上の制約による文法の記述の変更であるが,いずれも創作性を伴うようなものではない。 Ⅰ)は,G1Xver2.00 と同 ver3.00 では基本的に画面表示形式は同じであり,Ⅱ)は,Windows に対応して入力方法が変わることによるボタン,メニュー,入力項目のイベントの記述であるからプログラマーの個性が問題となるものではない。Ⅲ)は Windows に対応させるための作業にすぎず,Ⅳ)は,文法が異なる部分を修正するだけでプログラマーの個性が反映されるものではない。 なお,C 言語を VisualC++に変更するにあたって,基本的なモジュールはそのままコピーして使用できる。したがって,MS-DOS 対応 C 言語からWindows 対応 VisualC++言語への変更により,新たな創作性が生じることはない。 イ機能の追加等原告は,前記(1)イ 3)において,本件プログラムでは,G1X MS-DOS 版において RTM がその機能を担っていたマンマシン・インターフェイスを担う関数に特徴があると主張する。 しかし,原告の主張する関数は,RTM を用いる前から用いていたものであるから,Windows 版に対応するように記述したからといって何らの創作性が生じるものではない。 ウ新たに可能となった処理前記(1)ウにおいて原告が主張する機能の追加は,Windows という OS を用いることで付加された機能であり,Aが創作して付加した機能ではない。 (ア)前記(1)ウ①について(エクセルデータへの変換)エクセルデータへの変換のプログラム(甲36の3の「G1x.cpp」の 25ページ下から 1 行目から 27 ページ下から 15 行目まで)は,Windows のもとでは極めてありふれたプログラムで創作性はない。 G1Xver3.00のデータをエクセルデータに変換するには,Ⅰ)G1Xver3.00 からデータを切り取り,クリップボードにコピーして貼り付け,Ⅱ)クリップボードからデータを切り取り,エクセルにコピーして貼り付ける。逆に,Ⅲ)エクセルデータを G1Xver3.00 に変換する場合も,エクセルからデータを切り取り,クリップボードへコピーして貼り付け,クリップボードからデータを切り取り,G1Xver3.00 へのコピーして貼り付ける。 Ⅰ)のうち G1Xver3.00 のデータの「切り取り」「コピー」は,マイクロソフトの機能部品 MSFlexGrid を用い,クリップボードへの「貼り付け」は,MSFlexGrid の機能 GetClip を用いる。Ⅱ)のうち,クリップボードからのデータの切り取りは,マイクロソフトの関数 GetClipBoard により G1Xver3.00 の内部変数に保存し,クリップボードとエクセル間の相互のコピーはエクセルの機能によるもので,G1Xver3.00 の機能ではない。 Ⅲ)のうち,データの G1Xver3.00 への貼り付けは,MSFlexGrid のセルに順次貼り付ける。 これらの作業は,プログラマーであれば誰でも同様の処理をするもので個性が表れるものではない。 (イ)同②について(鳥瞰図表示)鳥瞰図表示のプログラム(甲36の3の G1xChokan.cpp)について,原告が創作性を主張する鳥瞰図の表示(乙50の 23 ページ)は極めてありふれたもので創作性はない。視点を移動できる点についても,平行移動,回転には行列計算を用いるが,これは数学上当然のものであり,プログラムとして目新しいものではない。陰線処理は,Zバッファ法(視点から物体への距離〔Z値〕について遠い〔Z値が大きい〕方から表示していくことにより,遠くの物体は近くの物体によって塗り替えられ立体感のある絵になるというもの)が用いられているが,当時でも鳥瞰図作成によく用いられたありふれたものである。 (ウ)同④について(カラー印刷)G1Xver3.00 にカラー印刷の機能はなく,フリーソフトの Wincap95 を使用していた。 G1Xver5.50 においてカラー印刷の機能は追加されたが(乙47の1のG1x.cpp の 31 ないし 34 ページ),次のとおり,他人が作成した公開ソフトをコピーして使用している可能性が高い。 すなわち,Ⅰ)Aは,プログラミングにおいてほとんどコメントを入れないが,カラー印刷モジュールでは多数のコメントが入っており,Aの記述スタイルとは異なる。Ⅱ)カラー印刷モジュール34ページ5行目には,「すべてのケースで GetD1Bits を使用する(1998.11.13)」という記載があるが,Aが作成していたとすれば,その時期は平成12年1月ないし4月であるはずである。Ⅲ)カラー印刷モジュール 34 ページ 8 行目には「Win95/98 では主にこちらを使用する」との記載があるが,橘高工学では,Win95/98 のOSを使用したことはない。 画面上に表示されたカラー表示をそのままカラー印刷するためのプログラムは従来から存する極めてありふれたもので,何ら創作性はない。 (エ)同⑥について(電源,再起動操作)他のコンピュータからの電源,再起動操作は,Windows が有する機能であり,原告が独自に作成したものではない。電源・再起動操作のプログラム(甲36の3の「G1xExit.cpp」2 ページ 14 行目ないし 4 ページ)と同じ記述がインターネット上でマイクロソフトのウェブサイトの MSDN ライブラリの「Displaying Shutdown Dialog Box」(乙53)に公開されている。相違点は,「return FALSE」が「Afx Message Box」に変更されている点だけである。したがって,Aは,MSDN ライブラリ内のプログラムをコピーしたにすぎない。 2本件プログラムの著作権の帰属(前記第4の1(2)の争点)(1)原告の主張アソースプログラムの保有・管理(ア)ソースプログラムの保有Aは,本件プログラムのソースプログラムを橘高工学に提出したことはない。 もっとも,G1Xver5.50 (G1X Lan.cpp,甲20)については,Aが,平成15年2月,被告の注文によりサハリンのホルムスク港において西村組のグラブ浚渫船にプログラムを納入した際,海外であり不具合等の場合に早急に対応をとる必要上,例外的にソースプログラムを西村組のグラブ浚渫船に限り残したところ,被告は,A及び原告に無断でこれを入手した(乙18は甲20とまったく同じである。乙47の1・2)。 (イ)被告の主張について被告は,Aが本件プログラムのソースプログラムを開示しなかったのは,被告がAないし原告に対し,バージョンアップや修補を専属的に依頼したので,特に必要がなかったからであると主張する。 しかし,仮に橘高工学に著作権が帰属していたのであれば,被告は,橘高工学から著作権の移転を受ける機会を有していたにもかかわらず,移転を受けなかったのであり,この事実自体が,Aに著作権が帰属していたことを認めていたことを示唆するものである。 イ対価の支払の有無(ア)開発費・著作権譲渡の対価の支払の有無Aは,G1Xver3.00 の開発や著作権の譲渡の対価として,橘高工学から開発費,修正費その他いかなる名目による金銭も受領していない。 (イ)被告の主張について被告は,橘高工学が平成12年1月にAに対し,新型ソナーに対応する第16堀松号用のプログラム(G1Xver3.00)を発注した際,仮払金を支払ったとか,外注加工費の仮払の支払約束があったと主張する。 しかし,本件各手形については「バック」させられているし,本件手形③ないし⑥はすべて不渡りとなっており,結局本件各手形のうち,現実にAに支払われたのは本件手形①のバック分(170万円のうち上乗せ分70万円の7割である49万円)を除く121万円のみである。 しかも,Aは,G1Xver3.00 の発注を受けたのと同じ日に,橘高工学から,G1W にソナー処理を付け足す改造依頼も受けており(改造費は未定),その他にも,当時(平成12年1月ないし4月ころ),複数のシステム開発やシステムの現地調整の受注をしていたので,手形により支払予定であった金銭も G1Xver3.00 の対価であると定まっていたわけではない。むしろ,Aとしては,平成11年に受注した本間組向け捨石均しシステムの現地調整費(交通費も含め109万円相当で作業は平成12年5月まで続いていた。)やフジタ向け水中打設システムの開発(新規システム開発費350万円相当)の開発費として支払われたものと認識している。 ウ各人の行動・認識(ア)橘高工学の行動・認識橘高工学の破産申立ての段階においても,宣告後の管財業務の段階においても,橘高工学に本件プログラムの著作権が帰属していたとの指摘はなく,橘高工学の破産管財人は,本件プログラムの著作権を処分したことがなく,橘高工学の財産として本件プログラムの著作権が存在するとの認識はなかった。 (イ)被告の行動・認識被告は,橘高工学の破産宣告後,Aに対し,橘高工学時代と同様の取引を継続したい旨を申し出て取引を開始したが,その際,後記のとおり,本件プログラム等についてソフト複製販売許諾契約を締結し,被告が納入先の顧客をAに報告し,Aが納品請求書を送付して,プログラム複製1セットにつき50万円の支払を受けていた。このように,被告は,本件訴訟提起まで,Aに本件プログラムの著作権が帰属することを前提とする行動をしてきた。 被告は,金銭の支払は橘高工学のAに対する損害の補償であると主張するが,Aの橘高工学に対する債権は,橘高工学の破産手続の終了により法律的に行使できなくなったので,損害補償をする必要性はないはずであり,にもかかわらず,損害補償的な意味も込めてAと取引を継続する必要があったのは,Aに本件プログラムの著作権が帰属し,それを利用する必要があったからである。メール(乙3)も複製許諾契約の存在を前提とするものである。 (ウ)Aの行動・認識被告は,Aが,平成16年4月までは,橘高工学ないし被告に対し,著作権者である旨の主張をしたことはない,橘高工学破産管財人に対して,自己に著作権が帰属するとして取戻権を行使したことはないと主張するが,それまでは橘高工学ないし被告から本件プログラムの開発及び利用に対する対価を受けており,Aにとっては著作権侵害の事実がなかったので,あえて著作権の権利行使をする必要がなかったのである。 なお,Aは,平成12年8月ころ,SKKの他にも,佐賀県の大潮建設に G1Xver3.00 を日本測器株式会社(以下「日本測器」という。)を経由して販売している。 エプログラム作成時の橘高工学からの指示の有無Aが,平成12年に G1Xver3.00 を開発した際,橘高工学は,G1X をVisualC++でバージョンアップするよう指示することも,言語を指定することもなく,Windows に対応するプログラムの開発を依頼したにとどまり,G1W とは別の独自プログラムを開発するのか,G1W をソナーに対応する形に追加,修正するかについての指示もせず,すべてAの裁量に委ねていた。 Aは,G1W を開発した際,G1W に必要な DLL は当時技術的に VisualBasicで作成することができず VisualC++で作成されたため,G1W を調整するにはVisualBasic と VisualC++の両方の開発ツールを使用する必要があるなど,調整が煩雑であり,安定性の点で VisualBasic は常時作動するか疑問があり,VisualBasic は故障時の原因追及が困難で,オーバーフロー時などに適切に対応することができないことなどの問題点があったため,GPS 処理ソフトGPAD VisualC++を橘高工学から指示されることなく,独自で開発し完成させていた。 Aが完成させたプログラムを現地調整する際は,橘高工学の従業員はAの指示に従って行動し,逆に,橘高工学からAに対する指示は全くなかった。 橘高工学では,従業員に対するプログラムに関する教育はほとんどなく,システムの説明等はすべてAに頼っており,橘高工学が指示したのは納期くらいであった。 オ著作権表示(ア)G1Xver3.00本件プログラムのうち G1Xver3.00 は,G1X の中核となる G1X.rc に「Nihon System Planning」ないし「A」の表示があるので(甲36の1,乙47の1の7),その著作権がAに留保されていたことは明らかである。 起動時画面には橘高工学の著作権表示が現れるが(乙50),過去に競業他社に無断で模倣されたことがあるので,競合他社によるソフトデザイン等の類似や同様のソフトの作成を防ぐ目的で,Aの個人名義より知名度の高い橘高工学の表示をしたものである。通常,著作権表示をソースに書き記す場合は,重要なソースの冒頭にするのが一般的であるところ,ソースプログラムの冒頭に著作権表示はないが,これは,Aがソースを橘高工学に提供していないので,無断利用のおそれがなかったからである。その後,橘高工学の破産に伴い,起動画面及びバージョン情報の記載を変更した。 なお,被告は,G1Xver5.50 の「CalhaVa.cpp」が G1Xver3.00 にないことについて不利な証拠を隠したと主張するが,同モジュールは座標計算テストをする際に G1X と同一フォルダに入れたものであり,実際の船体傾斜の位置補正ルーティンを内容とし,G1Xver3.00 のモジュール「G1x.cpp」の「RotZpr」「RotPr」をもとに作成した社外説明のためのソナー制御装置のプログラミング用のもので,G1Xver3.00 の一部ではなく,本来G1Xver3.00 に不必要なものである。 (イ)G1Xver5.24 ないし ver5.70本件プログラムのうち G1Xver5.24 ないし ver5.70 は,コンピュータ作動時にバージョン表示メニューを操作すれば,「(c)Copyright NihonSystem Planning」「Programer:A」という表示を確認できる(甲8)。 同プログラムの起動時にも数秒間,同じ表示が現れる。 カG1Xver3.00 の完成時期Aは,平成12年3月末ないし4月初めころ,G1Xver3.00 の暫定版を完成させ,橘高工学従業員Dに現地動作テストを依頼したが,潮位データの平均化が未了であったため,浚渫にバグが生じ,調整の必要が判明した。また,第16堀松号のソナー装置にトラブルがあり,同装置の動作検証ができなかったため,動作検証,バグの調整,総合検証は延期となり,この段階では,G1Xver3.00 は未完成であった。 プログラムは,動作環境に適応できるよう改変する必要があり,第16堀松号用の G1X は,本体及びオプションに対応できるようセットアップできる状態になって初めてプログラムとして完成したものといえる。また,プログラムは一体不可分のものであることから,ソナーに不具合があって G1X を検証,調整できないのであれば,それはプログラム全体の未完成を意味する。 SKKは,同年6月ころ,元橘高工学従業員のEを通じ,Aに対し,ソナー装置のトラブルが解消したとして,総合検証を依頼し,Aは,第16堀松号に出向いて現地調整を行い,総合検証を実施した後,同年7月3日,G1Xver3.00 を完成させ,SKKから,開発費及び現地出張費として335万円の支払を受けた。 したがって,G1xver3.00 が完成したのは,橘高工学の破産宣告後の同年7月である。G1Xver3.00 のファイルホルダーリスト(甲38)をみれば,同年4月以降も完成のための更新がされている。 仮に,同年4月に G1Xver3.00 が完成していれば,Aは,橘高工学に対し,直ちに開発費の請求をしているところ,実際には完成していなかったため,請求をしなかった。 なお,被告は,Aが納品書,請求書を交付していなかったと主張するが,甲40,甲41のとおり,納品と同時に,納品書,請求書を交付していた。 キシステム全体におけるプログラムの位置づけ被告は,取引先との関係ではグラブ浚渫管理施工システム一式が売買の目的であって,本件プログラムはその一部にすぎない旨主張するが,グラブ浚渫管理施工システムにおいては,G1X はシステムの全体を統括管理する重要な役割を担っているプログラムであって,単にシステムの一部にすぎないというものではない。むしろ,ハード部分は,大半既製品を集めて組み立てられたものであり,ハード部分だけでは競合他社との優劣の比較はできないし,営業においても,ハードの機能説明よりソフトの機能説明の方が,重要なアピールポイントになるものである。 クまとめ以上の事情からすれば,本件プログラムの著作権は,Aに帰属しており,その後に原告に譲渡されたのであり,Aから橘高工学に対して黙示の譲渡があったとは認められない。 (2)被告の主張アソースプログラムの保有・管理Aないし原告は,一部のソースプログラムを被告に開示していないが,被告は,原告ないしAに対し,バージョンアップや修補を専属的に依頼していたので,特にソースプログラムは必要がなかったからにすぎない。なお,被告は,G1Xver3.00 のオブジェクトプログラムを所持している(乙41,42)。 イ対価の支払の有無(ア)対価の支払橘高工学は,平成12年1月にAに対し,新型ソナーに対応する第16堀松号用のプログラムを発注した際,本件手形①②を振り出して仮払をした。Aは,本件手形①の手形金170万円のうち少なくともバック分を除いた121万円は受領している。本件手形③ないし⑥についても,バック分を除いた合計245万円については,不渡りになっていなければ,Aに支払われる予定のものであった。 (イ)原告の主張について原告は,上記の金員が G1Xver3.00 の対価として支払われたものではないと主張するが,橘高工学が同月に第16堀松号用のプログラムを納期を同年3月として発注し,同年2月ないし4月に外注加工費の仮払の支払約束がされて,本件各手形が振り出されているので,本件各手形の振出により支払約束された外注加工費仮払金には,G1Xver3.00 に対するものが含まれていた。 ウ各人の行動・認識(ア)橘高工学の行動・認識本件プログラムは,橘高工学に著作権が帰属する G1Xver2.00 をバージョンアップしたもので,橘高工学が開発したグラブ浚渫施工管理システム専用のプログラムであり,橘高工学は,本件プログラムを多数複製してグラブ浚渫施工管理システムのハードにインストールして,同システムを多数販売することを目的とし,その後のバージョンアップやデバッグを予定しているものであるから,橘高工学としては,複製の都度,Aに許諾料を支払うつもりで依頼したとは考えられず,従前同様,著作権は橘高工学に帰属するとの認識で多額の外注費を支払って外注していたので,本件プログラムの著作権は,当然橘高工学に帰属するとの認識であった。 (イ)被告の行動・認識原告は,被告が本件プログラム等について,ソフト複製販売許諾契約を締結していたと主張するが,否認する。後述するとおり,被告がAに支払った金銭は,橘高工学のAに対する損害の補償である。 (ウ)Aの行動・認識Aないし原告は,平成16年4月まで,本件プログラムの著作権者である旨の主張をしたことは一度もなく,橘高工学ないし被告に対し,複製許諾料を要求したことも,販売数量の報告を求めたこともない。Aは,橘高工学から外注を受け外注費を受領していたのみで,橘高工学が破産宣告を受けた際も,破産管財人に対して,自己に著作権が帰属するとして取戻権を行使したこともない。 エプログラム作成時の橘高工学からの指示の有無Bは,Aに対し,平成12年1月20日,「3月に堀松にソナー付きのものを納めるので準備するように」と指示した。 オ著作権表示(ア)G1Xver3.00G1Xver3.00 の取扱説明書(平成12年4月20日作成,乙50)にある起動時画面及びバージョン情報画面には「(c)Copyright by KittakaEngineering Laboratory Co.,ltd 2000 All Right reserved」「Programer A2000/3/12」「(c)Copyright Kittaka Engineering Laboratory Co.,ltd 」の表示が現れるが,これはA自身が記載したものである(乙49)。 Aは,橘高工学の破産宣告をきっかけに G1Xver3.00 に原告の著作権表示をしたにすぎない。被告は,橘高工学破産管財人からサーバの譲渡を受けたが,元従業員がパスワードを設定しており,開くことができなかったため,G1X MS-DOS 版の修正に関与し,ソースプログラムを有していたAに協力を求めることとしたが,Aはこのような状況を奇貨として,Aが著作権者である旨の表示をしたのである。被告は,取引先に納品するときに画面表示に橘高工学の著作権表示が出ると逆に困るので,Aがソースプログラムを所持していたこともあり,勝手に日本システム設計の著作権表示をすることを放置していた。 (イ)G1Xver5.24 ないし ver5.70G1Xver5.24 ないし G1Xver5.70 において,原告の著作権表示が現れるが(甲8),同表示画面はヘルプからバージョン情報に入ってようやく取り出しうるものであり,このシステムを購入した者がこの表示を認識することは希有である。また,G1X は,起動時に数秒だけ,原告の著作権表示が現れるが,あまりに短時間であることから,いずれも原告を著作者であると推定する根拠とはならない。 G1Xver5.50 のソースプログラムのモジュール「CalhaVa.cpp」のトップには平成12年2月1日付けで橘高工学の著作権表示が現れるので,G1Xver3.00 の4月版及び7月版のソースプログラムにも橘高工学の著作権表示のある「CalhaVa.cpp」が入っているはずであるが,原告が提出した甲36(G1Xver3.00 7月版のソースプログラム)に同モジュールはなく,原告は意図的に不利な証拠を提出していない。 カG1Xver3.00 の完成時期甲13によれば,G1X の初期バージョンは,橘高工学の破産宣告日より前の平成12年3月11日に作成されている。G1Xver3.00 の画面には,バージョン情報「2000/3/12」(乙42)の表示が現れる。 平成12年3月末に出荷準備がされた NAV-LAH Ⅲの装置の一部であるGPS受信演算装置には G1Xver3.00 が使用され,「NAV-LAH Ⅲ本体及び周辺機器製造番号表」(乙44)には,備考欄に「新型ソフト G1Xver3.00 使用」と記載されている。原告は,ソナーのトラブルがあったので,完成品とはならなかったと主張するが,ソナーはオプションであり,だからこそ G1W はソナー対応ではなかったし,G1Xver3.00 もソナーに関して不具合があったから完成していないとはいえない。 原告は,平成12年4月の時点で開発費の請求をしていないことをG1Xver3.00 が同時点で未完成であったことの根拠とするが,そもそも,Aは,橘高工学に対し,従来から納品書,請求書,明細書を交付していなかった(乙40の2ないし9は後日作成されたものである。)。Aは,同年3月ころに,G1Xver3.00 を完成したとして橘高工学に納品し,前記のとおり,外注加工費の仮払金も支払われていたが,同年5月に橘高工学が破産宣告を受けたため,上記外注加工費の精算には至らなかったにすぎない。 キシステム全体におけるプログラムの位置づけグラブ浚渫施工管理システムの売上に寄与するのは,全体的なシステムの使いやすさと施工管理の制度であって,プログラムの出来不出来ではなく,システム全体構成の出来不出来こそが問題となり,これらはすべて橘高工学の従業員により開発されている。 クまとめ以上の事情からすれば,Aは,橘高工学に対し本件プログラムの著作権を譲渡し,同一性保持権を放棄する旨の黙示の合意をしていた。なお,仮に,平成12年4月時点で G1Xver3.00 が未完成であったとしても,同プログラムは作成と同時に完成部分ごとに橘高工学に譲渡されていた。 3G1X MS-DOS 版の創作性の有無(前記第4の1(3)の争点)(1)原告の主張仮に,本件プログラムに独自の創作性がなく,G1X MS-DOS 版と同一の著作物であったとしても,G1X MS-DOS 版は,位置決めプログラムを超える独自の創作性を有し,位置決めプログラムとは同一の著作物ではない。 すなわち,位置決めプログラムは,単発的な船体の位置決めに関するプログラムにすぎず,船体を固定して位置決めが完了すれば役目は終了し,継続的に浚渫施工を管理する機能はないが,G1X MS-DOS 版は,浚渫の経過を常時記録し管理するものであって,作業データの内容の表示や施工データのメンテナンス等に関するプログラムが追加され,プログラムの分量も増大している。また,位置決めプログラムは,グラブ浚渫船のみならず,サンドコンパクション船等を含む種々の船の位置を決めるための汎用性を有するプログラムであるのに対し,G1X MS-DOS 版は,グラブ浚渫船という国内で総数100にも満たない特殊な船について,浚渫施工を管理する特殊なプログラムであり,その一部に船体位置決めに関するプログラムを含んでいても,プログラム全体としての機能,性質,内容は,位置決めプログラムとは全く異なる。 (2)被告の主張G1X MS-DOS 版は,Aに著作権が留保されていた RTM は別にして,それ以外の部分については,位置決めプログラムに付加的な変更(①従前は堀跡管理について深度認識スイッチを押すことで堀跡が画面上に表示されたが,新たに深度信号を自動で取り込み,その深度に伴う色づけを行うように変更した,②従前は方位角表現を本船の絵に基づく捻れ角表現をしていたのを,新たにインジケーター表現に変更した,③メインメニュー画面の項目を増やし見やすくした。)を加えたものにすぎず,独自の創作性はない。したがって,G1X MS-DOS版は,著作物としては位置決めプログラムと同一の著作物である。 4本件前プログラムの著作権の帰属(前記第4の1(4)の争点)(1)原告の主張アソースプログラムの保有・管理(ア)ソースプログラムの提出の有無Aは,当初,依頼を受けたソフトのソースプログラムはすべて提出していたが,橘高工学従業員が,位置決めプログラム NB 版を無断使用し,プログラム解説書を作成して,光波距離計のメーカーに提出したので,GDX等も G1W もソースプログラムを提出しなかった。G1Xver1.20 及びG1Xver2.00についても,そのベースである RTM のソースプログラムを厳格に管理していた。なお,Aは,Bから,著作権者である橘高工学にソースプログラムを提出するのは当然であると言われたことはない。 (イ)被告の主張について被告は,平成9年ころ,Aが G1X MS-DOS 版の微修正にあたり,橘高工学にソースプログラムを提出し,橘高工学の従業員がプログラムの内容をチェックして修正すべき内容を変更していたと主張する。 確かに,Aは,担当者が調整する便宜のため,G1X MS-DOS 版のソースプログラムを納入時に納入先のコンピュータに記録させていたが,当時出荷が増大し,Aは直接現地調整を行うことができなかったので,不具合等が生じた場合,橘高工学の従業員に,内容を報告させて電話等で指示を与えて修正させ,その修正に必要な部分のソースプログラムを渡したものにすぎず,プログラムの著作権まで譲渡したものではない。橘高工学の従業員は,ソースプログラムを理解した上でチェックすることはできず,せいぜい現地調整の段階において,Aの指示のもとに簡単な修正,訂正をするのみであった。 イ対価の支払(ア)昭和63年ころから平成3年ころまでAは,昭和63年から平成3年ころまで,橘高工学から,プログラムの開発費として,1時間当たりの単価にその月内にプログラム開発に従事した時間を乗じた額(月20万円ないし70万円)を開発費として受領していた。位置決めプログラム NB 版の対価は,開発期間2か月で90ないし100万円であり,GDX 等の開発の対価は150万円であった。 (イ)平成3年ころから平成6年ころまでAは,平成3年ころから,橘高工学からの申出により,月100万円の固定報酬で受注プログラムの開発に専従することになったが,橘高工学は,従業員が与えられるようなロッカー,机等の備品も一切貸与せず,橘高工学の従業員が出張先等からの連絡用に使用していた無料専用電話の番号さえAに教えなかった。 (ウ)平成6年ころから平成9年ころまでAは,平成6年ころ,橘高工学から依頼されるプログラムの仕事が多かったので,前年及び前々年の作業実績表を提示し,報酬の改定を申し入れたところ,橘高工学の専従ではなくなり,報酬も出来高払に変更されたが,報酬の一部はバックさせられていたので,実際に受けた報酬は平均月額100万円にも満たなかった。 SEの報酬は,経験年数や技量により考慮されるところ,当時経験10年以上のSEの相場は月100万円ないし180万円であり,Aの報酬は当時の相場の最低ランクであった。そして,Aは,本件前プログラム以外にも,開発工数が同等以上の他のプログラムも開発したのであり,開発費の内訳としては,他のプログラムの方が多い。 なお,橘高工学は,平成6年4月に販売したグラブ浚渫管理施工システムプログラムの販売定価を350万円ないし420万円,原価を70万円ないし90万円と設定していたが,原価の意味するものは,プログラムの仕入原価であると考えられる。 (エ)平成9年ころから平成12年まで被告は,橘高工学が平成9年から平成12年までに,Aに,手形交付により支払った金額は合計約5880万円,平成10年だけで2085万円以上であると主張するが,これには7割のバック分が含まれている。 ウ各人の行動・認識(ア)Aの認識・態度Aが,橘高工学破産管財人に取戻権を行使しなかったのは,著作権侵害の事実がない限り,あえて行使をする必要がなかったからにすぎない。 被告は,Aが橘高工学に対し,複製許諾料を請求したことも販売数量の報告を求めたこともないと主張するが,Aは,橘高工学から外注を受けて外注費を受領し,複製許諾料相当額が補償されていたので,格別著作権を主張する必要がなかった。 (イ)橘高工学の認識・態度橘高工学の破産手続において,橘高工学の財産として本件前プログラムの著作権があるとの認識はなく,同著作権は処分されていない。 エプログラム作成時の橘高工学の指示の有無(ア)位置決めプログラムAは,依頼を受けるにあたり,橘高工学から具体的な指示を受けていないし,開発のための具体的な詳細仕様書を示されたこともない。 橘高工学が,位置決めプログラム NB 版の開発をAに依頼した際,橘高工学は,ソフト仕様書(画面デザイン,ダイヤブロックチャート,ディテールフロー等を示したもの)を有しておらず,Aに対し,株式会社測器舎(以下「測器舎」という。)が作成した操作マニュアルソフトを示し,具体的な内容・方法はすべてAの裁量に一任するとの前提で依頼した。Aは,画面デザイン,操作性等を独自に設計して,位置決めプログラム NB 版を完成させたが,同プログラムは,測器舎のプログラムとは異なる画面,操作性を有するものであった。 被告は,Aが,乙25ないし乙30を前提に位置決めプログラム NB 版を作成したと主張するが,「作業船位置決めシステムの位置測定原理」(乙26)は,Aが位置決めプログラム NB 版を完成させた後に橘高工学従業員Hが作成したものであるし,位置決めプログラム NB 版はジャイロを用いていないので,「ジャイロを用いた船体位置決め」(乙27)は関係ないし,座標計算(乙28)及び変数リスト及びメインメニューのレイアウト(乙30)は,Aが作成した位置決めプログラム NB のソースプログラム及び乙15から橘高工学従業員Fが解析して作成したものである。 仕様書(乙29)のソフト部分は,国土総合建設従業員が橘高工学を訪れた際,Aは,ほぼ完成していた位置決めプログラム NB 版を作動させてデモンストレーションをしたが,このとき国土総合建設従業員から依頼されて作成した。「船体位置決めシステム座標計算ロジック」(乙15)も,Aが昭和63年に作成したものである。 また,被告は,位置決めプログラムについて,橘高工学が開発した自動追尾光波距離計による測量データを演算処理し,画面上に視覚的に表現するためのソフトであり,Aは,ハード部分の開発に何ら関与していない以上,具体的指示なくして修正できるはずはないと主張する。しかし,被告が橘高工学の特許に係る部分であると主張する位置計算ロジックの部分に対応するプログラムは,初等幾何学の知識で容易に導出できるものなので,被告の主張はあたらない。 (イ)G1X MS-DOS 版橘高工学が,GDX 等の開発をAに依頼した際,Aは,納入予定先から橘高工学の従業員を介して,プログラムの画面デザインの1つ(主要画面)を示されただけであり,それ以外のシステムに必要な他の画面(15枚)の設計及びそれに見合う機能を持つプログラムはAが開発した。当時,橘高工学の従業員には,C 言語でプログラムを作成できる者はおらず,Aは,橘高工学の従業員から,プログラムのデザイン,機能,操作等に関するアドバイスは一切受けていない。 オ著作権表示(ア)G1X MS-DOS 版G1X MS-DOS 版のメニュー画面には「Kittaka Engineering Laboratory」の表示があるが(乙38),これはユーザーのためにシステムの販売保守をする会社名をソフト上に記載しておくことにより,その会社の宣伝効果としての意味をサービスしたものである。「(c)Copyright」の表示を欠くから著作権の所在についての意味はない。 他方,同プログラムのソースプログラムには「autherA」の表示があり,「Kittaka Engineering Laboratory Co., Ltd」の表示もあるが(乙46の1),通常ソースプログラムには著作者と納入先を記載するのが慣例であり,その慣例に従って納入先の名称が記載されているにすぎない。 なお,被告は,RTM とそれ以外の部分を分けて,RTM の著作権はAに,それ以外の部分は橘高工学に帰属すると主張するが,G1X MS-DOS 版は,OSである RTM の管理下で作動するので,その開発は RTM がなければ困難であり,RTM と G1X MS-DOS 版の著作権が分離するようなことはない。 (イ)G1WG1W のトップメニューには,「(c)Copyright by Kittaka EngineeringLaboratory」の表示があるが(乙33),これは競合他社によるソフトデザイン等の類似や同様のソフト作成を防止する目的で,A個人より知名度の高い橘高工学の表示をしたものである。具体的には,オー・ケー・イーサービス株式会社が MS-DOS 版のシステムを新洋海工に売り込み,後にAは,上記システムが設置された36龍王丸のソフトを入れ替えたが,従前設置されていたシステムは G1XMS-DOS 版の模倣であることが明らかであったため,AとBは,模倣防止のための著作権表示の必要性について話したが,著作権譲渡の話はなかった。ソースプログラムには著作権表示はない。 なお,被告は,G1W ではマルチタスク機能のある Windows が用いられてい る の で , RTM は 不 要 に な っ た と 主 張 す る が , G1W に 用 い たVisualBasicVer5.0 はマルチタスク機能をサポートしていないし,RTM にはマンマシンインターフェース機能があり,その基礎的な考え方は G1W のプログラム内に取り込まれている。 (ウ)位置決めプログラム NB 版位置決めプログラム NB 版には著作権者の表示はなかった。 カ本件前プログラムの著作権の帰属Aは,位置決めプログラム NB 版の作成の際も,GDX 等の作成の際も,橘高工学から具体的な指示を受けておらず,開発費は受領していたものの,Aが橘高工学の指揮監督下において労務を提供するという実態はなく,橘高工学がAに支払った金銭も労働の対価であるとはいえず,ソースプログラムも,位置決めプログラム NB 版は提出したが,G1XMS-DOS 版及び G1W は,修正に必要な範囲でやむを得ず渡した分以外は,ベースとなる RTM も含めて提出していない。プログラムのメニュー画面に現れる表示に橘高工学の表示があっても,知名度の高い橘高工学の名を表示したものであって,著作権の所在の決め手となるものではない。 したがって,本件前プログラムはいずれも職務著作として橘高工学に帰属することはないし,本件前プログラムの著作権の黙示の譲渡も認められない。 G1X MS-DOS 版の著作権はAに帰属するし,位置決めプログラム NB 版の著作権もAに帰属する。 被告は,職務著作であると主張するが,職務著作であるというには,橘高工学が与えた指示がプログラマーに比肩するほど専門的な内容で,プログラマーであったAを単なる補助者にするような創作的作業を橘高工学がしたことが主張立証される必要があるところ,被告は橘高工学がしたという具体的な指示内容について何ら主張立証しない。 (2)被告の主張アソースプログラムの保有・管理(ア)ソースプログラムの提出の有無Aは,平成2年ころから平成5年6月ころまでは,橘高工学にソースプログラムを提出しなかったが,Bは,同年6月ころ,従業員からAがソースプログラムを提出しないのは不合理であるとの指摘を受けて,Aに対し,今後も発注する旨約束し,橘高工学が作成や改造を依頼したソフトは橘高工学のものであるから提出するのがあたりまえである,メンテナンスに必要であると伝えて,ソースプログラムを提出してもらった。 RTM については,Aからソースプログラム(乙46の2)の提出はあったものの,Aに帰属するものであり,橘高工学において無断使用しないでほしいとの申し入れがあったので,その旨約束したが,G1X MS-DOS 版については,このような申入れはないままソースプログラムが提出された。 Aは,平成8年ないし平成9年に,橘高工学にソースプログラムを提出し,橘高工学従業員からチェックを受け,橘高工学は,G1Xver2.00 のソースプログラムを保有していた。 (イ)原告の主張について原告は,G1X MS-DOS 版のソースプログラムを橘高工学に提出していたことを否認し,納入時に納入先のコンピュータに記録させていたと主張する。 しかし,被告が橘高工学破産管財人から譲り受けたパソコンのハードディスクに G1Xver2.00 のソースプログラム(乙46の1)は保管されていたし,乙18,乙46の1の10のソースプログラムに橘高工学の従業員による修正がされていることから,Aがソースプログラムを提出して橘高工学の従業員のチェックを受けていたことは明らかである。 イ対価の支払(ア)昭和63年ころから平成3年ころまで橘高工学は,Aに,位置決めプログラム NB 版の作成料としてかなり高額の金額を支払った。 (イ)平成3年ころから平成9年ころまでAは,平成3年ころから平成12年の橘高工学の破産宣告まで,専従外注として橘高工学の仕事のみをしていた。 橘高工学は,平成3年ころから平成6年ころまで,Aに対し,外注したものが完成していなくても,前払として外注費の分割払をし,全く仕事を依頼していないときも仮払処理で外注費を支払い,一定の外注が完了すると清算するというように,月100万円の固定報酬で実質的には労務提供の対価として外注費を支払っていた。Aは,橘高工学に対し,納品書も請求書も出していなかった。 平成6年以降も,Aは,原則として月100万円の報酬を受け,プログラム作成料が同額を超える場合には,追加して超過分の支払を受け,同額を下回る場合には,仮払として後に精算していた。 (ウ)平成9年ころから平成12年まで橘高工学が平成9年3月から平成12年2月までにAに支払った金銭は,合計約5880万円(月平均163万円)である。すなわち,橘高工学がAを受取人として振り出した約束手形は約9600万円で,うち約1200万円は貸付金(融通手形)で,残りのうち約2ないし3割は水増し分で,うち7割はAから橘高工学にバックされていた。平成10年では,手形振出額3141万円のうち400万円が融通手形,656万円が水増し分で,残りの2085万円(月平均173万円)が外注加工費(バージョンアップ代。出張交通費,宿泊費,工賃を含むが,その割合は少ない。)で,バックは水増し分656万円の7割の459.2万円である。 ウ各人の行動・認識(ア)Aの認識・態度Aは,本件前プログラムについて著作権者である旨の主張をしたことは一度もないし,橘高工学に対し,複製許諾料を要求したことも,販売数量の報告を求めたこともなく,外注を受け外注費を受領していたのみである。 Aは,橘高工学が破産宣告を受けた際も,破産管財人に対し,本件前プログラムが自己に帰属するとして取戻権を行使したこともない。Cが位置決めプログラム NB 版に修正を加え,同 QB 版を作成したことについても,橘高工学は,Aないし原告から何らの異議も受けていない。原告が著作権を初めて主張したのは,平成16年4月になってからである。 (イ)橘高工学の認識・態度橘高工学がAにプログラム作成を依頼した当時,著作権の帰属について明示の取決めはなかったが,橘高工学としては,動産の製造委託と同様に,納品がされて代金を支払えば,そのプログラムは橘高工学に帰属すると考えていた。位置決めプログラムは,橘高工学が開発した船体位置決めシステム専用のプログラムであり,橘高工学は,位置決めプログラムを多数複製して同システムの装置にインストールし,同システムを多数販売することを目的としていたので,位置決めプログラムの著作権は,当然橘高工学に帰属するとの認識であり,複製の都度,Aに許諾料を支払うつもりで依頼したとは考えられない。代金額も高額で,橘高工学は具体的な指示をしていたし,プログラムの用途も限定されていたので,Aも同様の認識であったと思われる。G1X MS-DOS 版は,位置決めプログラムを元に作成され,やはり他の用途に用いることができないものであるから,同様に考えるべきである。 エプログラム作成時の橘高工学の指示Aは,本件前プログラムの修正にあたってBから具体的な指示を受け,作業が終了すると,橘高工学の従業員にソースプログラムを提出し,作業内容についてチェックを受け,再修正がある場合にはさらに指示を受けていた。 (ア)位置決めプログラム橘高工学は,国土総合建設と共同で,「光波測距装置の使用方法について」(乙25),「作業船位置決めシステムの位置測定原理」(乙26),「ジャイロを用いた船体位置決め」(乙27),座標計算(乙28),仕様書(乙29),変数リスト及びメインメニューのレイアウト(乙30)を作成した。これらを前提として,Aは,橘高工学従業員から,光波測距装置の具体的内容,データの取込方法,データの構造等,位置計算ロジックの説明を受け,操作性や画面レイアウトについての具体的な指示を受けて,位置決めプログラム NB 版を記述した。その後のテスト,デバッグは,Aと橘高工学の従業員が協力して行った。 (イ)G1X MS-DOS 版橘高工学は,G1X MS-DOS 版の各発注時に,Aに詳細な技術説明を行い,プログラムの修正を依頼した。 オ著作権表示(ア)G1X MS-DOS 版GDX 等のトップページには,「Kittaka Engineering Laboratory」の画面が現れ,取扱説明書にも「株式会社橘高工学研究所」の記載がある(乙35)。G1Xver1.2 ないし G1Xver2.0 のメニュー画面には,「KittakaEngineering Laboratory」の画面が現れる(乙38)。 Aに権利が帰属する RTM については,「Copyright(c)Nihon systemplannig」の表示をしているのに対し,G1X MS-DOS 版には上記のとおり橘高工学の表示をしていることからすれば,Aは,G1X MS-DOS 版は橘高工学に帰属するという認識であった。G1X MS-DOS 版について,第三者にまねをされないためであれば,RTM 同様,「Copyright(c)Nihon system plannig」の表示でよいはずであり,同表示で足りないというのであれば,RTM にそのような表示をしていることに説明がつかない。 (イ)G1WG1W の ト ッ プ メ ニ ュ ー 画 面 ( 乙 3 3 ) に は , A 自 身 に よ り「(c)Copyright by Kittaka Engineering Laboratory」の表示がされている。 (ウ)位置決めプログラム NB 版位置決めプログラム NB 版には橘高工学の表示が現れる(甲25)。 カ本件前プログラムの著作権の帰属(ア)職務著作上記のとおり,橘高工学とAとの関係は,実質的には,橘高工学の指揮監督下においてAが労務を提供するという実態にあり,橘高工学がAに対して支払う金銭は労務提供の対価と評価できるので,本件前プログラムは,いずれも橘高工学の発意に基づき作成されたプログラムであって,職務著作として,橘高工学が著作者である。 (イ)黙示の譲渡の合意仮に,本件前プログラムが職務著作ではなかったとしても,Aは,橘高工学従業員から指示を受け,同従業員と協力しながら,本件前プログラムを作成・完成させたので,本件前プログラムは,橘高工学従業員との共同著作であるし,橘高工学にソースプログラムを提出し,プログラムに橘高工学の表示がされ,Aは橘高工学の指示により高額の作成料でプログラムを作成し,ライセンス料の請求をしたことがない等の上記の事情からすれば,Aは,橘高工学に対し著作権(共同著作と認められる場合は持分)を譲渡し,同一性保持権を放棄する旨の黙示の合意をしたといえる。 特に,位置決めプログラムについては,Aはソースプログラムを橘高工学に提出し,バージョンアップにAは関与せず,Cが修正追加をし,その後のプログラムに橘高工学の著作権表示があることからしても,譲渡されていることは明らかである。 その他の本件前プログラムについても,著作権譲渡の明示的な書面はないが,橘高工学は,Aに対し,かなり高額の作成料を支払っていることから,Aが著作権を留保しているとは考えがたい。G1X MS-DOS 版はいずれもグラブ浚渫施工管理システム NAV-LAH の GPS 受信演算装置にインストールして用いるものであり,他の用途はなく,橘高工学が製造するハード専用で橘高工学以外の者が利用することはできないことからしても,橘高工学がAにプログラムのバージョンアップを依頼する際,それらのプログラムの著作権は橘高工学に帰属することを当然の前提としていたものである。 (ウ)橘高工学から被告への譲渡橘高工学破産管財人は,平成13年3月,被告に対し,特許権及び動産一式を譲渡したが,その中にはプログラムが保存されたサーバも含まれており,プログラムの著作権も売買の目的物として被告に移転している。そのプログラムの中には G1X MS-DOS 版も含まれている。 仮に,橘高工学から被告への G1X MS-DOS 版の著作権の譲渡が認められないとしても,橘高工学以外の者に著作権が帰属することとなるものではない。 (エ)まとめG1X MS-DOS 版は,創作性がないので(二次的)著作物ではなく,位置決めプログラムと同一の著作物であり,位置決めプログラムの著作権が,橘高工学に帰属する以上,G1X MS-DOS 版の著作権も橘高工学に帰属する。仮に,G1X MS-DOS 版が著作物ないし位置決めプログラムを原著作物とする二次的著作物であったとしても,G1X MS-DOS 版の著作権も橘高工学に帰属する。 5著作権の権利主張についての対抗要件の要否(前記第4の1(5)の争点)(1)被告の主張原告は,Aから本件プログラムの著作権を譲渡されたと主張するが,著作権移転のための対抗要件である登録をしていないので,被告に対し,著作権を有していることを主張できない。 (2)原告の主張著作権の移転を登録しなければ対抗できない「第三者」とは,登録の欠缺を主張する正当な利益を有する者であり,被告のような著作権を侵害する者は「第三者」には該当しない。したがって,原告は,登録なくして被告に対し,本件プログラムの著作権を主張することができる。 6著作権に基づく差止請求についての侵害のおそれの有無(前記第4の1(6)の争点)(1)被告の主張被告は,現在,G1Xver5.24 ないし同 5.70 をグラブ浚渫施工管理システムに使用していないので,差止請求の要件である「侵害のおそれ」はない。 (2)原告の主張否認ないし争う。 7著作権侵害についての被告の故意過失の有無(前記第4の1(7)の争点)(1)原告の主張被告は,従前,Aとの間で,本件プログラムにつき複製販売許諾契約を締結し,本件プログラムの供給を受けていたのであるから,著作権の帰属に十分な注意をすべきであり,著作権法に詳しい弁護士に相談すれば,本件プログラムの著作権がAに帰属していたことを容易に知り得た。被告は,十分な調査も検討もすることなく,独善的にAが著作権者ではないと思いこんでいるにすぎず,少なくともそのことにつき過失がある。 (2)被告の主張争う。被告は,橘高工学の破産管財人から橘高工学の動産,特許権等を譲り受けて,橘高工学と同種の営業を始めたものであり,Aも自ら G1Xver3.00 のトップページに「(c)Copyright Kittaka Engineering Laboratory Co.,Ltd 2000All Right Reserved」と表示していた。したがって,仮に,本件プログラムの著作権の一部がAに帰属していたとしても,被告が橘高工学に帰属していたと認識していたことについて過失はない。 8著作権侵害による損害発生の有無及びその数額(前記第4の1(8)の争点)(1)原告の主張本件プログラムの複製許諾料は1セットにつき50万円が相当であり,被告は少なくとも20セットを複製販売した。したがって,Aが被った損害は,1000万円をくだらない。 また,Aは,著作権侵害の事実調査のため,別紙3のとおり13万2005円を要した。 よって,被告がAの著作権を侵害したことによる損害は1013万2005円である。 (2)被告の主張損害の発生及びその額は否認ないし争う。 なお,被告がAに,50万円又は80万円を支払っていたのは,後述のとおり,橘高工学時代の損失を補償する趣旨である。 9本件プログラムについての複製許諾契約の有無(前記第4の2の争点)(1)原告の主張ア本件プログラムの複製販売許諾契約Aと被告は,平成12年11月ころ,本件プログラムにつき,複製販売1セットにつき50万円を支払うとの約定で,プログラムソフト複製販売許諾契約を締結した(以下「本件複製販売許諾契約」という。)。 被告は,納入先の顧客をAに報告し,Aは,納品請求書を送付し,被告は,Aに,50万円ないし80万円を許諾料の一部として支払っていた。 イ損害の填補であるとの主張について被告は,Aに50万円又は80万円を支払っていたのは,Aの橘高工学に対する債権の損害填補として贈与したものであると主張する。 しかし,Aの橘高工学に対する債権は,橘高工学の破産手続の終了により法律的に行使できなくなったのであるから,填補の必要はないはずである。 にもかかわらず,被告がAと取引を継続する必要があったのは,Aに本件プログラムの著作権が帰属し,これを利用することが必要だったからである。 被告がAに宛てたメール(乙3)の記載は,Aが被告との契約に基づき作業をしていた事実や本件複製販売許諾契約が存在していたことを前提とするものであって,50万円の支払が損害補償のための贈与ではないことを示すものである。 (2)被告の主張ア本件複製販売許諾契約の主張についてAと被告との間で,本件複製販売許諾契約を締結した事実はない。G1XMS-DOS 版ないし本件プログラムの著作権は橘高工学に帰属し,Aに帰属していなかったので,被告がAから許諾を受ける理由はない。Aは,プログラムにプロテクトもしていない。なお,原告は,本件複製販売許諾契約の締結は平成12年6月ころであると主張していたが,その時期には橘高工学が破産宣告を受けており,Bは,Aと複製販売許諾契約等について話をしていない。 イ損害の填補被告がAないし原告に対して金銭を支払ったのは,損害補償として贈与したものである。 すなわち,橘高工学は,破産宣告時,Aに対し,549万円の債務を負っていた。被告が,橘高工学と同種の営業を行うに当たり,Aの協力なしで円滑な業務を行うことはできなかったので,取引を依頼したところ,Aから,回収不能となった橘高工学の債務の支払を求められた。被告は,資力がなく,一括支払が不可能であったため,資金にゆとりができる都度,損害補償をすることをAに約束した。 被告は,Aに対して,50万円ずつ6回,80万円ずつ3回の合計540万円を支払ったが,分割して支払ったのは,被告が取引先から受注を受け,資金にゆとりが出る都度,支払ったのであり,納品書及び請求書を同時に送付しているのは,税金対策として適当な名目をつけたにすぎない。平成13年1月10日付け納品書(甲1の1)の「坂口工業向けソフトバージョンアップ」については,その内容の仕事はしていないことをA自身が認めている。 10本件 GPADver4 開発契約に基づく代金の支払拒絶の可否(前記第4の3(1)の争点)(1)被告の主張本件 GPADver4 開発契約に基づく代金10万5000円については,本件GPADver4 ソフトにバグがあり,同ソフトは動かなかったため,未完成であるから,代金の支払義務はない。 バグの内容は,乙11のとおりであり,本来であれば,いずれの公共基点,いずれの測地系を選択しても作動するはずであるところ,GPAD ver4.0 は,世界測地系を選択しても,基点座標は別のソフトを用いて変換した日本測地系に基づく座標値を入れないと,偽の座標値が出力されるという不具合があり,原告自身も,甲10で「Gpad Version4.20S Version4.0 の基準座標不具合を訂正」と記載して,不具合があったことを認めている。 GPADver4.1s の場合,公共基点Ⅰ(RTCMデータ・フォーマット)には対応しない。 (2)原告の主張被告は,本件 GPADver4 ソフトにバグがあり,同ソフトは未完成であるため,その代金を支払わなかったと主張する。 しかし,Aが被告に本件 GPADver4 開発契約に基づいて本件 GPADver4 ソフトを供給したのは平成15年10月ころであるが,当時,被告からは同ソフトにバグがあるとの連絡はなく,平成16年5月ころに至って,突如,同ソフトに不具合がある旨の連絡があったが(乙3),その時点においても不具合の内容についての詳細な説明はなかった。 そこで,Aが詳細を被告従業員に確認したところ,GPAD ver4.0 は,基地局の座標入力(同一工事現場で設定は1度。同一工事現場は数か月間続く。)において日本測地系の座標を入力すれば,システムは正常に機能するとのことであった。そして,実際にユーザーがこの状態で使用している以上,同ソフトにバグがあって動かないとはいえない。被告自身も,基点座標の座標値をわざわざ別ソフトを用いて日本測地系の座標値に変換しなければならないと主張しているように,変換ソフトを使用して変換すればよいのであり,同ソフトは「バグがあって動かない」とはいえないから,代金支払を拒絶する根拠とはならない。 GPADver4.1s については,否認する。対応しないの意味も不明であるし,原告は,本件訴訟における被告の主張により,初めてその旨を知らされたのであり,同ソフト供給当時は被告からは何ら苦情はなかった。 11相殺1の成否(前記第4の3(2)の争点)(1)被告の主張被告は,次のとおり,原告に対し,債務不履行による損害賠償債権を有している。 アAは,本件斜杭打設管理ソフト変更契約により,被告が販売する本件斜杭打設管理ソフトを,被告に無断で競業他社に販売しないという信義則上の義務を負った。すなわち,被告は,Aに対し,本件斜杭打設管理ソフト変更契約を締結して外注加工費を支払ったのであり,注文者としては当然その成果物及び提供した情報を,注文者の利益のためにのみ用いることを予定し,競業他社に対して類似のソフトを販売することを禁止していたし,契約書に明文がなくても,継続的な外注加工依頼がされていた以上,受注者の善管注意義務,信義則上の不作為義務が生じる。 イにもかかわらず,原告(Aが法人なりしたもの。)は,被告のためにAが保管していた被告の本件斜杭打設管理ソフトを複製して,平成15年10月に中国の某会社向け斜杭打設管理システムソフト(以下「本件中国向けソフト」という。)を競業他社に納品した。古野電気は,船舶用重機の施工管理システムの製造販売を目的とする会社であるところ,株式会社アムテックスに対し,斜杭打設管理システムソフトを発注し,その際,原告のソフトを使用することを指定した。 ウ本件中国向けソフト(乙51)は,次のとおり,本件斜杭打設管理ソフト(乙52)と同一のものである。したがって,本件中国向けソフトは,Aが被告のために保管していた本件斜杭打設管理ソフトの複製物である。 ①画面の構成が同一である。 ②取り込むデータの項目が,旋回角,ジブ角,トリム,ヒール,アウトリーチであり同一である。これは重機のどの部分からどのように測定するかという点において共通していることを意味する。 ③取り込んだデータを演算して杭の設計位置と現在の杭の位置とのズレ量を表示するシステムであるところ,その演算結果,表示方法も同じである。 ④取り込みデータ,演算内容,表現方法がすべて同じである。 ⑤乙51の1添付の画面タイトルバーには,「第一豊号 斜杭打設管理システム Ipx Ver1.00」と記載されているが,これは本件斜杭打設管理ソフト(乙52)と同じ名称である。原告は,本件斜杭打設管理ソフトをそのまま本件中国向けソフトとして古野電気に納品した。 エ原告が上記の行為をしなければ,被告は,上記の注文を受注できたはずであり,斜杭打設管理システムの価格は1800万円で,利益額は少なくとも1000万円であるから,被告には得べかりし利益相当額1000万円の損害が生じた。なお,杭打船に関するマンマシンソフトは,他社が製造しておらず,そのノウハウ(センサーの取付位置,センサーからのデータ処理のアルゴリズム等)は被告が独占し,平成15年当時,斜杭打設工管理システムを製造販売する業者は国内では被告のみで,被告がシェアを独占していたので,原告が本件中国向けソフトを提供しない限り,確実に被告が受注できたものである。 オよって,被告は,原告に対し,Aの契約における信義則上生じる義務違反により,1000万円の損害賠償債権を有している。 カ原告の主張について原告は,本件斜杭打設管理ソフトの著作権はAに帰属すると主張するが否認する。本件斜杭打設管理ソフトは,橘高工学が開発し,その後修正を施したもので,Aは,上記の修正に関与したにすぎない。 (2)原告の主張ア販売禁止義務の有無本件斜坑打設管理ソフトは,Aが平成3年9月20日に創作したもので,その著作権はAに帰属する。したがって,原告が被告から斜坑打設管理ソフトを競業他社に販売することを禁止されることはない。 本件斜杭打設管理ソフトは,橘高工学の依頼により開発したが,実際の杭打ちの演算における高度な3次元空間における演算ロジックはAが考案し,このノウハウをもとに同ソフトを作成したのであり,橘高工学は,依頼時にセンサーなど機器構成図を示したのみで,ソフト開発をAに一任し丸投げ状態であった。そして,上記機器構成図は被告独自のノウハウではない。なお,Aは,橘高工学に対し,同ソフトのソースプログラムも渡していない。 イソフト画面の同一性乙51と乙52のソフト画面は同一であるが,乙51のソフト画面は,原告が古野電気に対し,単なる営業資料として提出したものであり,原告が実際に中国に納入した本件中国向けソフトの画面は次の点で異なる。 Ⅰ)杭頭(杭の打止め高さ)の管理について,測量員が光波計を用いて行っていたのを本件中国向けソフトでは自動計測(リアルタイム)とした。 Ⅱ)GPS を2台使用して重機の姿勢を計測しているとき,旋回時 GPS の1台に,電波の遮断等による計測不良が頻繁に生じるが,本件中国向けソフトでは,対処法として別個の GPS 方位計測器を設置して船体の誘導を可能とした。 Ⅲ)本件中国向けソフトでは,リーダーの上部と下部の支点間距離が可変となっている。 Ⅳ)本件中国向けソフトでは,各種センサーのデータを手動入力し,シミュレーションを行うこともできる。 Ⅴ)本件中国向けソフトでは,すべての画面の文字を中国向け仕様にし,ひらがな,カタカナを使用せず作り替えた。 12相殺2の成否(前記第4の3(3)の争点)(1)被告の主張被告は,次のとおり,原告に対し,不正競争防止法2条1項14号,4条に基づく損害賠償債権を有している。 ア競争関係原告は,主にコンピュータソフトの開発,販売,賃貸を業務内容とする会社であり,被告は,主に業務用ナビゲーションシステムの開発,製造,販売,修理,賃貸を業務内容とする会社で,両者は,ナビゲーションシステムの関連ソフト開発,製造,販売,修理等において競争関係にある。 イ営業上の信用を害する事実の告知・流布本件送付文書には,「弊社製」という表現が用いられており,原告が「グラブ浚渫ソフト」(G1W,G1X,RTPS,GPAD)を開発し,原告が著作権を有する「グラブ浚渫ソフト」について,被告が原告の許諾を得ることなく,あるいは許諾の範囲を超えて複製しているかの印象を与える。 したがって,本件送付文書の被告取引先への送付は,被告の営業上の信用を害する事実の告知・流布である。 ウ告知・流布された事実が虚偽であること「グラブ浚渫ソフト」のうち,G1W 及び G1X MS-DOS 版については,橘高工学及び被告の開発,製作によるもので,Aはプログラマーとして関与したにすぎず,ましてや原告の製作によるものではないし,その著作権は原告に帰属するものではない。 GPAD 及び RTPS については,カナダの WayPoint 社のプログラムであり,被告がライセンスを受けて利用していたもので,Aの関与は,橘高工学の発注に対し,インターフェース部分についてマニュアルどおりに設定したにすぎない。 本件送付文書の表現からすれば,あたかも「グラブ浚渫ソフト」の著作権が原告に帰属し,原告が被告にライセンスしているかのような誤解を受けるので,本件送付文書の送付により告知・流布された事実は虚偽である。また,本件送付文書の記載内容は,被告は原告に対して販売報告義務があると誤認させる点でも虚偽である。 したがって,上記原告の行為は,不正競争防止法2条1項14号に該当する。 エ故意・過失原告は,プログラムを扱う者である以上,著作権の帰属には十分に注意すべきであり,橘高工学の時代からの開発経緯も知っているので,これを整理して著作権法に詳しい弁護士に相談すれば,原告にグラブ浚渫ソフトの著作権がないことは容易に知り得たはずであるから,原告には少なくとも過失がある。 オ損害の発生及びその数額上記の原告の行為により,被告は営業上の信用を毀損され,その損害損害額は合計500万円をくだらない。 (2)原告の主張争う。 第6当裁判所の判断1著作権に基づく請求についての争点の整理と判断の順序本件においては,船体位置決めプログラムを前提として,G1X MS-DOS 版,本件プログラムという順番で,プログラムが順次作成されているところ,著作物性に関しては,船体位置決めプログラムの著作物性は争いがなく,G1X MS-DOS 版及び本件プログラムの著作物性は争いがある。他方,プログラムの著作権の帰属については,船体位置決めプログラム,G1X MS-DOS 版,本件プログラムのいずれについても争いがある。 したがって,①本件プログラムが著作物であり,その著作権は原告に帰属する,②仮に,本件プログラムが G1X MS-DOS 版の複製であって著作物性がないとしても,G1X MS-DOS 版が著作物であり,その著作権は原告に帰属する,③仮に,G1XMS-DOS 版が船体位置決めプログラムの複製であって著作物性がないとしても,船体位置決めプログラムの著作権が原告に帰属する,のいずれかが認められれば,原告は,本件プログラムの複製販売の差止めを求めたり,同プログラムの著作権侵害による損害賠償請求をすることができる。 もっとも,上記①(本件プログラムが著作物であり,その著作権は原告に帰属する)が認められたとしても,それが二次的著作物であって,原著作物に付加された部分が小さい場合などには,原著作物の著作権の所在も,損害額の認定において相当額の決定に影響を与える。 そこで,本件では,まず,本件前プログラム及び本件プログラムをめぐる事実経過(後記2)について認定した後に,時系列の順序に従って,G1X MS-DOS 版の創作性の有無(後記3),本件前プログラムの帰属(後記4)について判断し,次に本件プログラムの創作性の有無(後記5),本件プログラムの帰属(後記6)について判断し,これらの判断を前提として,損害額について判断する(後記9)。 2本件前プログラム及び本件プログラムをめぐる事実経過前記第3の前提となる事実,証拠(各事実の末尾に記載)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる(争いのない事実も含む)。 (1)位置決めプログラムについてアソースプログラムの保有・管理Aは,位置決めプログラム NB 版のソースプログラムを橘高工学に提出し,Cが変更を加えたり,QuickBASIC 版を作成し,橘高工学の著作権表示を付した(乙23,24,31の2)。もっとも,A自身も位置決めプログラムNB 版のソースプログラムは保有していた(甲15,25,28)。 イ対価の支払(ア)当時の報酬支払状況(位置決めプログラム NB 版以外も含む)Aは,昭和63年から平成2年ころまでは,プログラムの開発につき時間制でその月内にプログラム開発に従事した時間に乗じた金額を開発費として完成後に支払を受けていた。(原告代表者12ページ,被告代表者1ページ)(イ)位置決めプログラム NB 版の対価位置決めプログラム NB 版の対価としては,橘高工学はAに対し,開発期間2か月(昭和63年9月から10月まで)として,総額90万円ないし100万円を開発費として支払った(甲44)。なお,平成6年当時,「浚渫用位置決めソフト」は,複製物の販売価格(定価)は320万円,標準仕切価格は215万円,最低仕切価格は30万4000円,原価すなわち開発に要した費用は20万円とされている(原告代表者14,15ページ,甲42)位置決めプログラムは,Cにより改変された後,複製されて船体位置決めシステムにインストールされて,橘高工学の著作権表示を付した状態で橘高工学により販売されていたが,個々の販売に際して,Aは調整等に関与しておらず,対価も受けていない。(前記第3の2(1)イ)ウ橘高工学からの指示橘高工学は,測器舎の操作マニュアルと通信ルーチンを示して詳細な仕様書を示さず,また,プログラム言語の指定もすることなく,Aに位置決めプログラムの作成を依頼した。Aは,昭和63年当時,一般的によく使用されていた日本電気株式会社製のパソコンで使用できるよう,プログラム言語として N88BASIC を選択して,画面及び操作性は測器舎のものとは異なる内容で,位置決めプログラム NB 版を作成した。 橘高工学からAに対して具体的な指示がなかったことについては,被告が具体的に指示するために示したと主張する資料のうち,「座標計算」(乙28)は,位置決めプログラム NB 版の作成後,FがA作成のプログラムを解析して作成したものであるし(甲29),「座標計算ロジック」(乙15)及び「自動追尾光波距離計製作仕様書」(乙29)は,A自身が作成したもので,これらはいずれも,Aがプログラム作成にあたり橘高工学から示されたものではなかった(被告代表者は,その尋問において〔調書33ページ〕,乙29は国土総合建設の従業員が作成したと述べるが,筆跡及び乙29の5ページの「終予」の字の誤りの記憶に関する原告代表者の説明からすれば,Aが作成したものと認められる。)。(原告代表者5ないし7,48ないし52,56,57ページ,被告代表者28,33ページ,甲44)エ著作権表示位置決めプログラム NB 版のソースプログラムの冒頭には「Kittakaengineering laboratory Co.,Ltd」の文字が記述されているが(甲25),メニュー画面やバージョン画面等に「(c)Copyright」の表示は現れない(甲15)。 位置決めプログラム QB 版には,「(c) Copyright Microsft / KittakaEngineering Laboratory Co.,Ltd.1989 All Right Reserved.」の表示が現れる(乙23,24)。 オ汎用性位置決めプログラムは,グラブ浚渫船,サンドコンパクション船等,様々な種類の海洋土木作業船の船体の誘導位置決めに使用することができる船体位置決めシステムに対応するプログラムで,グラブ浚渫施工管理システムに対応するプログラム(GDX 等,G1X シリーズなど)の前提となるものでもあった。(原告代表者7ページ)(2)G1X MS-DOS 版,G1W についてアソースプログラムの保有・管理(ア)G1X MS-DOS 版Aは,平成3年ころから平成5年ころは,GDX 等のソースプログラムを橘高工学に提出していなかったが,平成5年ころ,橘高工学から提出するように指摘され,その後,橘高工学から要求があった場合はソースプログラムを提出していた。Aは,現場で修正が必要な場合に備えて,G1XMS-DOS 版のソースプログラムを納入時に納入先のコンピュータのハードディスクに記憶させていた。G1X MS-DOS 版について,平成8年6月ころ,橘高工学従業員Fが,平成9年5月ころ,橘高工学従業員Gが,修正及びコメントを加えている。(原告代表者46,59,60ページ,甲44,乙18,19)(イ)RTMRTM については,そのヘッダーファイル「rtm.h」のみが橘高工学に提出されているが,それ以外のソースプログラムは橘高工学に渡されておらず,AとBとの間で,その著作権がAに帰属することについて確認していた。(原告代表者46ないし48,59,60ページ,被告代表者2ないし4ページ,甲44)(ウ)G1WAは,G1W のソースプログラムを橘高工学に提出していない(乙58)。 イ対価の支払(ア)当時の報酬支払状況(G1X MS-DOS 版及び G1W 以外も含む)a平成2年ころから平成6年ころまでAは,平成2年ころは,個別に注文書により受注・対価の決定をしていたが,平成3年ころから平成6年ころまでは,月100万円の固定報酬で受注プログラムの開発に専従していた。(被告代表者1ページ,甲44,乙54)b平成6年ないし平成8年ころから平成10年ころまでAは,平成6年ないし平成8年ころ以降は,橘高工学の専従ではなくなり,出来高払で開発費を受領していたが,報酬の一部(約7割)は「バック」させられていたため,実際に受領した金額は平均で月約100万円であった(原告代表者12,27ないし29ページ,被告代表者4,5ページ,甲40,44,乙54)。なお,当時,10年以上の経験があるSEの報酬の相場は,月額100万円から180万円であった。 (甲37,44)c平成10年及び平成11年平成10年及び平成11年における橘高工学からAへの金銭の支払状況は,別紙4のとおりであり,約束手形により支払われた。Aから橘高工学への「バック」分及び橘高工学からAへの貸付分を除いた実払額は,平成10年で月100万円ないし200万円(合計1551万円。月平均約130万円),平成11年で40万円ないし240万円(合計1257万円,月平均約100万円)であった(被告代表者5ないし13ページ,甲40,乙55,56)。 BとAは,毎月20日ころ,1か月分の支払額について話し合い,Aがその場で請求書等を発行し,Bが約束手形を振り出して支払っていた。 なお,Aが発行した請求書(甲40)の内訳は,Bに言われたものを記載したものであって,実体を表しているものではない。(原告代表者10,11ページ。なお,甲40と乙55,56,58の添付別表は平成10年の部分について,金額的にはほぼ一致するが,明細は一致しない。)(イ)個別のプログラムの対価aG1X MS-DOS 版の対価平成2年9月11日に発注された GDX 等の開発(開発費,客先への納品・インストール作業,オペレーターへの指導・インストレーション)の対価は「2船分」(青木組所有船向けと小島組所有船向け。プログラムの販売自体は青木組に2船分)で150万円であった。橘高工学は,青木組から上記プログラムの開発費用として1船分につき200万円ないし300万円を請求していた。(原告代表者11ないし14,40ページ,甲30)橘高工学は,平成6年4月に販売した GDX 等の複製物を定価350万円ないし420万円,実売価格を200万円ないし300万円で販売していたが,うち原価すなわち開発ないし修正に要した費用は70万円ないし90万円に設定されていたから,これが原告に支払われた費用と推認される。また,上記実売価格からすれば,GDX 等の著作権を譲渡する場合の相当な価格は,上記実売価格を大きく上回るものと推認される(Aは2000万円をくだらないと供述する。)。(原告代表者14,15ページ,被告代表者2,34,35ページ,甲42,44)G1Xver1.62(平成10年2月ころコンパイル)までは,対象の作業船ごとにプログラムを調整する必要がありバージョンが変更されていたが(そのために「GDX 等」のプログラムの名称も,GDX,GDT,GOT,GDM,GSM,GTM,GSX,G2X,88KYO,18RYU,25RYU などと作業船ごとに細かく異なっている。甲14,40,乙34,35,55など),橘高工学はその調整をAに依頼し,Aは,調整の都度,修正費ないし改造費として橘高工学から報酬を受けていた。したがって,Aは,橘高工学が複製販売したプログラムの数をほぼ把握していたが,G1Xver1.62 以降については,特に船ごとに修正ないし改造を加えなくても,多種多様のグラブ浚渫船に対応できるようになったため,Aは,橘高工学によるG1Xver1.62 以降のプログラムの複製販売数を把握していない。(原告代表者16,62ページ,甲44。なお,G1Xver2.00〔乙46の1〕のソースプログラムには複数の船名の記載がある。例えば「G1X_MODE」〔乙46の1の15〕には「18東照号」「38海栄号」「25龍王丸」「21須山丸」の記載がある。)bG1W橘高工学は,Aに対し,G1W の開発費として300万円を支払った(被告代表者37ないし39ページ,甲40,乙55)。 ウ橘高工学からの指示(ア)GDX 等橘高工学が,GDX 等の開発をAに依頼した際,Aは,納入予定先から橘高工学の従業員を介して,プログラムの画面デザインの1つ(主要画面)を示され,それ以外の画面(15枚)の設計及びそれに見合う機能を持つプログラムはAが開発した。当時,橘高工学の従業員には,C 言語でプログラムを作成できる者はおらず,Aは,橘高工学の従業員から,プログラムのデザイン,機能,操作等に関するアドバイスは受けていない。(被告代表者29ページ,甲44)(イ)G1W橘高工学は,平成11年,Aに対し,G1X MS-DOS 版を Windows に対応させるよう開発の依頼をしたが,プログラム言語の指定はなかった。 Aがプログラム言語として Visual Basic を選択して G1W を作成したのは,Ⅰ)VisualBasic は VisualC++に比して容易に開発できるよう工夫された独特の開発環境と共に提供された言語で手軽であり,Ⅱ)当時,Aは,Windows 対応 Visual Basic を用いたプログラムを数例組んだ経験はあったものの,Windows 対応 VisualC++によるプログラム開発の経験はなく,Ⅲ)納期も考慮したことによる。なお,このころ,Aは,GPAD の VisualC++版を開発しており,G1W についても,GPAD の DLL の部分は,当時の VisualBasic で作成することは不可能であったため,VisualC++で記述しなければならなかった。(甲44)エ著作権表示(ア)GDX 等GDX 等の画面のトップページには,会社名等の表示は一切ないものもあるが(甲17,乙17,平成2年11月ころのバージョン。甲18,平成3年1月ころのバージョン),「Kittaka Engineering Laboratory」の表示が現れるものもある(乙35,平成6年11月ころのバージョン。乙34,平成7年11月ころのバージョン)。 なお,原告は,GDX 等のソースプログラムにはAの著作権表示が入っていた旨主張するが(平成17年8月29日付け第6回準備書面4ページ),原告は GDX 等のソースプログラムを保有しているはずであるにもかかわらず,それを提出しない。 (イ)G1Xver1.20 ないし G1Xver2.00G1Xver1.20, G1Xver1.50, G1Xver1.61, G1Xver1.61B, G1Xver1.61C,G1Xver1.62,G1Xver2.00 のメニュー画面には,「Kittaka EngineeringLaboratory」の表示が現れ(乙36ないし乙38,うち乙36はG1Xver1.50 の平成9年10月のバージョン),G1Xver2.00 のソースプログラムの冒頭には「Kittaka engineering laboratory Co.,Ltd.」の表示があるが,これらは納入先を記載したものである。他方,G1Xver2.00 に使用されている RTM のソースプログラムの冒頭には,「Copyright(c) Nihonsystem plannning 」の表示がある。(原告代表者58,59ページ,乙46の1・2)(ウ)G1WG1W のメニュー画面には,「Copyright(c)by Kittaka EngineeringLaboratory」の表示が現れるが,これはAが記載したものである(原告代表者24ページ,乙33)。 オ汎用性GDX 等は,各作業船ごとに改造,修正をすれば,他のグラブ浚渫船に用いることができ,当時,グラブ浚渫施工管理システムを導入できる可能性のあるグラブ浚渫船は国内で100隻くらいあった。(原告代表者15ページ)(3)G1Xver3.00 についてアソースプログラムの保有・管理Aは,G1Xver3.00 のソースプログラムを橘高工学に提出しておらず,橘高工学も同プログラムのソースプログラムを保有していない(乙58)。 イ対価の支払Aは,G1Xver3.00 の対価として,橘高工学に対し,1セットあたり250万円で合計2セット(堀松建設向けと大潮建設向け)分500万円(消費税抜き)を請求したが,橘高工学からは支払を受けることができず,平成12年7月以降に,SKKから335万円(消費税抜き。うち300万円が開発費で35万円が現地調整費)を受領した(原告代表者19,38ないし41ページ,甲7,33,40,44)。 ウ橘高工学からの指示G1Xver3.00 の開発にあたり,橘高工学からプログラム言語の指定はなかった。 Aは,G1W を Windows 対応 Visual Basic で完成させていたが,Ⅰ)G1W のうち DLL を用いる部分については VisualC++で作成するなど,Visual Basic を使用する場合でも VisualC++を一部併用しなければならず,Visual Basic のままでは調整が煩雑であったこと,Ⅱ)当時 Visual Basic は故障時の原因追及が困難で,オーバーフロー時等に適切に対応することができない等,安定性の点で疑問があったこと,Ⅲ)平成11年にすでに GPAD は VisualC++のものを開発済みであったことから,G1Xver3.00 については VisualC++を使用することとした。(甲44)エ著作権表示(ア)画面表示G1Xver3.00 の「G1x のバージョン情報」の画面には「(c)CopyrightNihon System Plannnig 2000 All Rights Reserved」の表示が現れる(甲36,乙1,442)。他方,Aが作成した G1Xver3.00 の平成12年4月付けの取扱説明書(乙50)に載せられているシステムの起動時画面,バージョン情報画面には,「(c)Copyright Kittaka Engineering LaboratoryCo.,ltd. 2000 All Rights Reserved」の表示がある。(原告代表者24,25ページ,乙50)(イ)ソースプログラムの記載G1Xver3.00 のソースプログラムのうち G1X の中核となる G1X.rc には「(c)Copyright」「Nihon System Planning」「2000-2003 All RightReserved」の記述の表示がある(甲36の1,乙47の1の7)。 G1Xver5.50 に含まれているモジュール「CalHaVa.cpp」の冒頭には「Copyright(c)by Kittaka engineering Laboratory Co.,Ltd」の記載があるが(乙47の2の1),モジュール「CalHaVa.cpp」は,G1Xver2.00(乙46の1)及び G1Xver3.00(甲36)には含まれていない。 オ汎用性Aは,平成12年8月ころ,日本測器経由で,大潮建設に G1Xver3.00(販売価格200万円)を販売した。(原告代表者19ページ,甲7)(4)G1Xver5.24 ないし ver5.70 及び被告設立後の状況アソースプログラムの保有・管理Aは,本件プログラムのソースプログラムを橘高工学ないし被告に渡していない。そのため,橘高工学の破産宣告後,被告は,取引再開をAに依頼した(被告代表者本人19ページ)。 被告が書証として提出している G1Xver5.50 のソースプログラム(甲20,乙18,乙47の1・2)は,Aが,サハリンのホルムスク港で西村組のグラブ浚渫船にソースプログラムを残したものについて,被告の従業員ないしBが持ち帰ったものである(被告代表者本人43ページ,甲44)。 イ対価の支払(ア)金員の授受被告は,平成12年10月ころ,Aに対し,グラブ浚渫施工管理システムのプログラムの供給を依頼し,Aは,同年11月ころから,既に開発済みの本件プログラムのオブジェクトプログラムを被告に納入するようになった。Aは,バージョンアップ等の作業をし,その支払を受けているが,例えば次のとおり,作業をしていない分についても,50万円ないし80万円を受領したことがある。(被告代表者17ないし19ページ,甲44)a納品書(甲1の1)の「坂口工業向けバージョンアップ費」50万円については,被告は,本件プログラムに関して,ソフト及びハードを代金800万円強で坂口工業に納品したが,Aは「坂口工業向け」のプログラムの作成等の作業をしていない。 b納品書(甲1の2)の「大新土木向けソフトバージョンアップ費」50万円については,被告は,代金約400万円で MS-DOS のプログラムを Windows のプログラムに入れ替える作業をしたが,Aは「大新土木向け」のプログラムの作成等の作業はしていない。 c納品書(甲1の15)の「伯新 G1X ソフト一式」については,被告はAに代金20万円でプログラムの改造を依頼したが,実際には50万円を支払った。 (イ)金銭授受の趣旨Bの認識としては,被告がAと取引を開始するにあたって,Aから橘高工学時代の損失補償を求められ,G1Xver3.00 等のソースプログラムはAが保有し,その意味において被告はAより弱い立場にあったたため,Bは,Aの要望を容れて損失補償をすることとし,G1X 関係のプログラムが販売された際に,その修正費・改造費に付加する形で,あるいは具体的に仕事の発注はないが発注があったかのような名目で,50万円ないし80万円ずつ,合計540万円(別紙5の「売上高」欄に記載されている数字に黄色のマーカーがされている部分)を支払った。(被告代表者16ないし20ページ,乙58)Aは,訴状8ページ下から3行目以下において,被告が橘高工学時代の「負債を補償すると約束した」ので被告との取引に応じることとしたと述べ,被告から報酬として受領した金員の一部(実際にした仕事の対価を超える額)あるいは具体的な仕事なくして受領した金員について,少なくともその一部は損失補償の趣旨であったと理解していた(原告代表者22,23,42ないし44,訴状8ページ,平成16年12月8日付け原告の第1回準備書面2ページ)。なお,授受のあった金員の名目は「ソフト料」「バージョンアップ費」等であったが,Aは,被告との間で,その実質はライセンス料であるとの確認はしていない。(原告代表者61,62ページ)もっとも,上記「損失補償」は支払時期や金額が決まっていたのではなく,被告は,橘高工学がAに与えた損失と認識していた金額(約540万円)を支払い終わった後も,支払を終わらせると言えば,A(原告)が,損失額を増加させて主張したり,他の理由で金銭の要求をすることを予想しており,G1Xver3.00 等のソースプログラムを保有しているA(原告)からプログラム(バージョンアップ版)の供給を絶たれることを恐れて,金銭の支払の終了や支払うべき金額の確定を申し入れたことはなかった(乙58,被告代表者19,20ページ)。 ウ著作権表示本件プログラムのうち G1Xver5.24 ないし ver5.70 は,コンピュータ作動時にバージョン表示メニューを操作すれば,「(c)Copyright Nihon SystemPlanning」「Programer:A」という表示を確認できる(甲8,乙47の1)。 同プログラムの起動時にも数秒間,同じ表示が現れる。 3G1X MS-DOS 版の創作性の有無(前記第4の1(3)の争点)(1)前記第3の前提となる事実,証拠(各事実の末尾に記載)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる(争いのない事実及び前記2で認定した事実も含む)。 ア昭和63年当時の船体位置決めシステム及び位置決めプログラム NB 版昭和63年当時の初期の船体位置決めシステムは,作業船に設置された光波距離計測装置における2台の自動追尾光波距離計を用いて,船体の位置を計算するのに必要な距離や水平角のデータを求め,次に,各データが作業船内のコンピュータに送付され,「船台位置決め方法」により,上記の送付されたデータを作業船内のコンピュータで位置演算処理をして,船体位置を計算するものであった。各データと演算処理された結果は,それぞれ座標の数字及び座標上の位置図として,作業船内のコンピュータの画面ディスプレイに表示された。 なお,プログラムを作成したAの感覚では,位置決めプログラム NB 版は,比較的単純で,Aの経験と技量によれば短期間で完成できるものであった(弁論の全趣旨・原告の平成17年9月16日付け第7回準備書面2ページ)。 イ平成2年ころ以降のグラブ浚渫施工管理システム及び GDX 等GDX 等は,船体位置決めシステムを前提とするものであるが,船体の位置決めと,堀跡の管理の機能を有するプログラムである。 (ア)船体位置決めの機能平成2年ころ以降のグラブ浚渫施工管理システムにおける船体位置決めの機能は,従来の船体位置決めシステムにあった2台の自動追尾光波距離計によるデータ収集に加え,重機に備え付けられた旋回角計,ジブ角計,深度計のセンサーからのデータの取込みが可能となり,あらかじめ入力された船体の寸法に基づいて演算処理をして,船体の位置情報及びグラブバケットの位置情報を計算し,これらを画面ディスプレイにリアルタイムで表示するものであった。 (イ)平成2年当時のグラブ浚渫施工管理システムのうちの堀跡管理の機能は,上記の船体位置決めの機能において取得したデータや潮位に関するデータ等を基に,堀跡指示用データ入力装置を付加して堀跡の演算処理を行い,画面ディスプレイに平面図での1工区ごとの浚渫堀跡深さ等を表示するものであった。(乙17)(ウ)橘高工学は,平成2年10月ころ,船体位置決めシステムに堀跡管理機能を付加して構成することを企画して,「グラブ浚渫工事施工管理装置計画仕様書」(乙17)を作成した。 船体位置決めプログラム NB 版の画面(甲15)と GDX 等のうちの一つであり,18東照号向け仕様として作成されたグラブ浚渫施工管理プログラム GOT Ver.1.0(平成4年11月3日作成,平成6年4月7日ソナー仕様に変更。甲14)の画面(乙35)を対比すると,両者は,メインメニューも異なるうえ,例えば,タイトルとしては似ており船体位置決めに用いるものと認められる「船体の属性入力画面」(甲15)と「船体属性の設定画面」(乙35)も,入力すべき項目が,前者は「基準点と距離計の相互距離」であるのに対し,後者は「船体の形状,船首からの旋回中心の距離,光波計位置(座標系で入力)」等と異なるうえ,画面表示も大きく異なるなど,全体として共通性に乏しいことから,GDX 等は,単に,従来の船体位置決めプログラム NB 版に堀跡管理のプログラムを付加したにすぎないものであるとは認めがたい。 また,プログラムを作成したAの感覚では,G1X MS-DOS 版ないし本件プログラムにおいて船体位置決め機能の占める割合は,堀跡管理機能の占める割合に比して小さかった。(原告代表者本人8ないし9ページ)ウ平成8年ころ以降のグラブ浚渫施工管理システム及び GNX ないし G1X シリーズ平成8年当時の GPS 装置付きグラブ浚渫施工管理システムは,その名称もLAH シリーズから NAV-LAH シリーズに変更され,船体位置決めの方法は,自動追尾光波距離計と GPS 装置のいずれかを選択できるものとなり,プログラムにおいても GPS 装置に対応する部分が追加された。 GPS 装置に対応する部分のプログラムの最も特徴的な部分である RTK 演算部分は,WayPoint 社が作成した GPS 処理システムソフトの DLL のプログラムないしモジュールが用いられていた。 GDX 等(平成4年ないし平成5年ころ)のモジュール数が13であったのに対し,平成8年以降の GNX ないし G1X シリーズのモジュール数は,通信制御,描画,重機処理,LAN処理などが追加されて22となり,各モジュールの更新も繰り返されている(甲14)。 (2)G1X MS-DOS 版の創作性の有無以上のとおり,グラブ浚渫施工管理システムは,船体位置決めの機能を担う部分についても,それ以前の位置決めシステムと比較して,処理内容が,重機に備え付けられたセンサーからのデータ(旋回角計,ジブ角計,深度計)等を計測し,これらのデータとあらかじめ入力された船体の寸法データに基づいて演算処理をして,船体の位置情報及びグラブバケットの位置情報を計算する方法と光波計による方法とを一体化して全体として船体位置決めをするというように相当複雑になっており,各プログラムの画面においても共通性が乏しい。 これに加えて,G1X MS-DOS 版が位置決めプログラムに用いられていた N88BASIC や QuickBASIC とは言語体系が全く異なる C 言語で記載されていることからすれば,G1X MS-DOS 版は,プログラムの表現方法に選択の幅が十分にあるうちから作成者が選択したものであって,作成者の個性が表れているものと認められる。 また,新規追加された堀跡管理機能も,GDX 等の浚渫管理メニュー画面(甲17)をみると,「工区メッシュ設定」「潮位設定」「浚渫作業」「工区座標の設定」「仕掛りデータの編集」「出来高データの編集」等といった項目があり,新規追加された堀跡管理機能の処理部分の内容の複雑さ及びそれらの処理に必要と推測されるプログラムの量からすれば,そのプログラムの表現方法には選択の幅が十分にあり,その中から作成者が選択した表現であって,作成者の個性が表れているものと認められる。 なお,G1X MS-DOS 版は,平成2年の GDX 等の作成以降,モジュール数が増加し,機能も追加されているが,これらの各プログラムはいずれも G1X MS-DOS版の他のバージョンからの複製又は翻案にすぎないものと認められる。 以上より,G1X MS-DOS 版(GDX 等から G1Xver2.00 まで)は,位置決めプログラムと同一の著作物ではなく,少なくとも,位置決めプログラムを原著作物とする二次的著作物であるということができる。 なお,G1Xver1.20 ないし G1Xver2.00 は,RTM のもとで作動するものであり,RTM は,Aに著作権が帰属する著作物であるが,それ自体は OS であって,G1Xver1.20 等とは別個の著作物であることはいうまでもない。 (3)被告の主張について被告は,G1X MS-DOS 版は,RTM を除くと,位置決めプログラムに付加的な変更を加えたものにすぎず,その内容は,①従前は堀跡管理について深度認識スイッチを押すことで堀跡が画面上に表示されたが,新たに深度信号を自動で取り込み,その深度に伴う色づけを行うように変更した,②従前は方位角表現を本船の絵に基づく捻れ角表現をしていたのを,新たにインジケーター表現に変更した,③メインメニュー画面の項目を増やし見やすくしたというものであるから,独自の創作性はないと主張する。 しかし,前記(1)(2)で認定したとおり,位置決めプログラムと GDX 等を比較すると,被告が主張するように,単に画面表示を変更して使いやすくしただけの相違ではないことは明らかであるから,被告の主張は採用できない。 4本件前プログラムの著作権の帰属(前記第4の1(4)の争点)について(1)G1X MS-DOS 版の著作権の帰属アG1X MS-DOS 版の開発経緯及びその後の事情(ア)開発時の報酬の金額前記2において認定したとおり,橘高工学は,平成2年ころ,Aによるプログラムの開発につき,個々の注文書により発注・対価の決定をし,Aに対し,平成3年ころ以降は月100万円の固定報酬を支払っていたが,平成2年11月に作成された GDX 等の対価としては,開発費(客先への納品・インストール,オペレーターへの指導・インストレーションも含む。)は「2船分」で150万円を支払い,客先である青木組に対しては開発費用として,1船分につき200万円ないし300万円を請求していた。また,橘高工学は,平成6年4月ころ販売していた G1X MS-DOS 版について,定価を350万円ないし420万円,実売価格を200万円ないし300万円と設定し,開発ないし修正に要した費用(原告に支払った費用)は70万円ないし90万円としていた。上記実売価格からすれば,GDX 等の著作権を譲渡する場合の対価は上記実売価格を大きく上回り,Aの供述する2000万円をくだらないとの金額も,誇張ともいえないものと認められる。 橘高工学は,平成6年ないし平成8年ころ以降は,Aに対し,プログラムの開発について出来高払で開発費を支払っており,その額は「バック」分を除くと月平均約100万円で,平成10年,平成11年も同様の状況であった。GPS 装置付きグラブ浚渫施工管理システムに対応するプログラムの初期版(GNX)の対価は,甲40の24枚目の平成9年1月20日付け「NAV-LAH・LAH 一体化ソフト開発」の金額が220万円とされていることから,約220万円であったと推認される(前記のとおり,甲40は,実際の項目と金額が一致しているわけではないが,G1Xver1.10 が完成したのが平成9年5月であり〔甲14〕,時期的に近接していること,従前の本件前プログラムの具体的対価,当時の支払状況などから,そのように推認される。)。 (イ)ソースプログラムの管理前記2において認定したとおり,Aは,位置決めプログラム NB 版のソースプログラムを橘高工学に渡したところ,Cにより,そのプログラムのノウハウを使用されたことから,平成3年ころから平成5年ころは,一般的にソースプログラムを橘高工学に提出しなくなり,GDX 等のソースプログラムも橘高工学に提出していなかった。しかし,平成5年ころ,橘高工学からソースプログラムを提出するよう求められ,そのころから,橘高工学からの要求に応じて G1XMS-DOS 版のソースプログラムを提出し,現場で修正が必要な場合に備えて,G1X MS-DOS 版のソースプログラムを納入時に納入先のコンピュータのハードディスクに記憶させていた。実際に,平成8年6月ころ,橘高工学従業員Fが,平成9年5月ころ,橘高工学従業員Gが修正及びコメントを加えている。もっとも G1X MS-DOS 版は,RTM のもとで作動するものであり,Aは,RTM のソースプログラムをヘッダーファイルを除いて橘高工学に渡していないし,橘高工学との間で RTM の著作権がAに帰属することを確認している。 なお,G1Xver1.62(平成10年作成)までは,対象の作業船ごとにプログラムを調整する必要があり,Aが橘高工学から依頼を受けてバージョンを変更していたので,Aは,その変更内容を承知していたし,調整の都度,修正費ないし改造費として橘高工学から報酬を受け,橘高工学が複製販売したプログラムの数をほぼ把握していた。 (ウ)著作権表示前記2において認定したとおり,GDX 等の画面のトップページには,「Kittaka Engineering Laboratory」の表示が現れ,取扱説明書にも「株式会社橘高工学研究所」の記載があるが,これらは納入先(プログラムが組み込まれるシステムのメーカー)の名称を記載して,システムのユーザー(上記メーカーの顧客)等にメーカー名を認識させようとしたものと考えられる一方で,「(c)Copyright」等が付された著作権表示は橘高工学のものもAに関するものもない。 G1Xver1.2 な い し G1Xver2.00 の メ ニ ュ ー 画 面 に は , 「 KittakaEngineering Laboratory」の表示が現れ,G1Xver2.00 のソースプログラムの冒頭には「Kittaka engineering laboratory Co.,Ltd.」の表示があり,これらは納入先を記載したものと考えられるが,その画面ないしソースプログラムに「(c)Copyright」等が付された著作権表示は橘高工学のものもAに関するものもない。 G1Xver2.00 に使用されている RTM のソースプログラムの冒頭には,「Copyright(c) Nihon system plannning 」の表示がある。 ただし,G1W にはAが自ら橘高工学の著作権表示を付している。 イG1X MS-DOS 版の著作権の帰属(ア)著作権譲渡の対価の支払の有無についてプログラムの著作権を譲渡する場合,当然のことながら,譲渡後は,譲渡人は同プログラムの著作権(著作者人格権を除く)に関して何らの権利も有さなくなるのであって,同著作権に係る著作物を自らも複製・頒布・翻案することができない上,第三者が同著作物を複製等しても,同著作権に基づく差止請求,損害賠償請求をすることもできなくなる。他方,譲受人は,同著作物を複製・頒布・翻案することができるし,第三者(譲渡人も含む)による同著作物の複製等に対して,同著作権に基づく差止請求や損害賠償請求をすることができる。 このように,著作権を譲渡するということは,著作権法21条ないし28条が規定する著作者の権利を全て譲渡するということであり,対象となる著作物の経済的価値が大きければ大きいほど,譲渡する著作権の対価も高額なものとなるのは当然である。そして,著作物の経済的価値の大小については,同著作物の複製物が販売されている場合は,その販売価格の多寡が参考となる。 本件において,G1X MS-DOS 版の著作権の譲渡の対価であると評価することができる程度の額の金銭の授受の有無について検討すると,GDX 等の開発から G1X シリーズの開発ないし修正に至るまで,例えば,GDX 等の複製物が少なくとも一船分200万円ないし300万円で販売されていることに見合うような著作権譲渡の対価が,著作権の譲渡時に授受されたと認めるに足りる証拠はない。 むしろ,G1X MS-DOS 版については,GDX 等の複製物が一船分200万円ないし300万円で販売されるものについて,Aは,システムを導入する作業船に併せてプログラムを修正し,複製物が作業船所有者に納品,販売される際に,一船につき70万円ないし90万円等の報酬を受領していたというものであった。このことからすると,G1X MS-DOS 版に関してAに支払われた対価は,著作権の譲渡代金ではなかったと思われる。 (イ)ソースプログラムの提出についてAは,G1X MS-DOS 版のソースプログラムを橘高工学に提出し,現場で修正が必要な場合に備えて,G1X MS-DOS 版のソースプログラムを納入時に納入先のコンピュータのハードディスクに記憶させている。 しかし,Bの説明(乙54)によっても,これは,平成5年ころ,今後の仕事がなくなるのではないかと心配するAに対し,Bが,①今後の注文もAに回すことを約束し,②橘高工学が依頼してAが作成したプログラムはもともと橘高工学に帰属するから,ソースプログラムを提出するのは当り前である,③納品した製品のメンテナンスにソースプログラムは必要であると説得した結果であるというのである。 そうすると,上記のBの説明は,Aが,ソースプログラムを開示すると,橘高工学にとってそのソースプログラムに基づく G1X MS-DOS 版の修正(複製の範囲内に止まる修正と翻案となる修正の両方を含む)が可能となるため,これを恐れてソースプログラムを提出しなかったのに対し,橘高工学が,Aのプログラムを他人に利用されない権利(複製の範囲で修正する権利及び翻案権)を尊重することを約束した趣旨であるように解される。 なお,その際,Bは,「橘高工学が依頼してAが作成したプログラムはもともと橘高工学に帰属する」と説明したというのであるが,これは,当該特定のバージョンの複製物の所有権ないしこれに伴う権利(デッドコピーすることの許諾も問題となるが,平成5年ころは,特定のバージョンをデッドコピーして他の船に使用することはできなかったから,この時点でそこまでの意味があったとは認められない。)を指していると理解する余地がある。したがって,上記Bの説明によるソースプログラム提出の経緯は,Aが G1X MS-DOS 版について著作権(翻案権及び複製権)を有している(譲渡していない)ことと矛盾するものではない。 (ウ)プログラムの複製についてG1X MS-DOS 版は,G1Xver1.62 までは,対象の作業船ごとにプログラムを調整する必要があり,橘高工学はその調整をAに依頼していたため,橘高工学がAに対する「バージョンアップ代金」「ソフト修正代」名目での支払なしにプログラムの複製物を販売したことはなかった。 また,G1X MS-DOS 版は,平成5年ころに RTM が開発された後には,RTMのもとで作動するもので,RTM についてはAが著作権を主張し,そのソースプログラムを管理し,Bは,RTM を無断使用せず,これを使用するようなソフトを作成する場合にはAに依頼することを約束していた(被告第17準備書面)。 したがって,G1X MS-DOS 版を大きく翻案して,新たな創作性が加えられたプログラムをAの承諾なく作成して販売する場合は,依然として RTM を使用するプログラムとなってしまい,RTM の著作権侵害となるとともに,Aに対する約束違反にもなると考えられる。 このことからすれば,G1Xver1.62 以降は,橘高工学はAの関与なしにプログラムの複製物を販売することができるようになったものの,その著作権が橘高工学に譲渡されたのではなく,Aが,橘高工学による当該バージョンのデッドコピーを許諾ないし黙認していたにすぎないものと解される。 (エ)著作権表示G1X MS-DOS 版の各ソースプログラムないしメニュー画面に,橘高工学の表示が現れるが,これらについて「(c)Copyright」等が付された著作権表示はなく,単にAから見た納入先である橘高工学の名称を記載したものにすぎないと考えられる。そして,Aが自ら G1X MS-DOS 版のプログラムに橘高工学の著作権表示をしたり,第三者によって橘高工学の著作権表示がされている状況を放置・黙認するといった事実はない。 (オ)まとめこれらの事情に鑑みれば,Aは,G1X MS-DOS 版の著作物について,橘高工学に特定のバージョンのデッドコピーによる複製,譲渡を許諾ないし黙認していた可能性はあるものの,その著作権自体までも橘高工学に譲渡し,自らの著作権を失ってしまったと評価することはできない。 したがって,G1X MS-DOS 版の著作権はAに帰属し,同著作権は,平成18年5月までにAから原告に譲渡されているので,原告に帰属する。 ウ被告の主張について(ア)共同著作・黙示の譲渡の合意の主張についてa被告は,Aは,橘高工学従業員から指示を受け,同従業員と協力しながら,G1X MS-DOS 版を作成したので,G1X MS-DOS 版は,橘高工学従業員との共同著作であると主張する。 しかし,技術的説明や指示をしたとしても,そのことにより直ちにプログラムの表現をしたことにはならないところ,被告が,橘高工学のG1X MS-DOS 版の各発注時に,プログラムの表現に関わる技術的説明や指示をしたと認めるに足りる証拠はない。また,デバッグや検収の作業を橘高工学の従業員とAが協力して行ったとしても,デバッグはプログラムの修正の作業にすぎないから,同修正により新たに創作性のある表現がされたといった特段の事情のない限り,そのプログラムが橘高工学の従業員とAの共同著作となるものではない。 b次に,被告は,Aは,橘高工学にソースプログラムを提出し,プログラムに橘高工学の表示をし,橘高工学の指示に基づきかなり高額の作成料でプログラムを作成し,ライセンス料の請求をしたことがない等の事情からすれば,著作権譲渡の明示的な書面はなくても,橘高工学に対し著作権(共同著作と認められる場合は持分)を譲渡し,同一性保持権を放棄する旨の黙示の合意をしたと主張する。 しかし,プログラムにある橘高工学の表示は,前記のとおり,著作権表示ではなく,むしろ,納入先の名称を記載したものにすぎないと認められることは前示のとおりである。 プログラムの作成料ないし開発費についても,前記のとおり,著作権譲渡の対価といえる程度に高額な報酬が支払われたものではないことは前記のとおりである。 また,橘高工学にソースプログラムを提出したとしても,そのことによって直ちに著作権を譲渡したとすることはできない。かえって,橘高工学が,プログラムの修正はAに発注することを約束していたことは,B自身認めるところであり,A自身もソースプログラムを管理しており,自ら複製,翻案することも可能な状態であった。 cさらに,被告は,G1X MS-DOS 版がいずれもグラブ浚渫施工管理システム NAV-LAH の GPS 受信演算装置にインストールして用いるものであり,他の用途はなく,橘高工学が製造するハード専用で橘高工学以外の者が利用することはできないから,橘高工学がAにプログラムのバージョンアップを依頼する際,それらのプログラムの著作権は橘高工学に帰属することを当然の前提としていたと主張する。 しかし,前記2で認定したとおり,GDX 等は,改造,修正を加えれば,他のグラブ浚渫船に用いることができ,当時,グラブ浚渫施工管理システムを導入できる可能性のあるグラブ浚渫船は国内で100隻くらいあったのであり,汎用性がまったくなかったものではない。 dなお,G1W は,Aが自ら橘高工学の著作権表示を付している。 しかし,G1X MS-DOS 版は C 言語で記述されているのに対し,G1W は,系列の異なる Visual Basic で記述されている。このように,G1W は,G1X MS-DOS 版とは別言語による別バージョンとして橘高工学に納入されたものであるから,仮に,G1W に係る権利を橘高工学に移転する旨の合意があったとしても,G1W に係る権利の移転に伴って G1X MS-DOS 版の権利が移転する契約があったとまで認めることもできない。したがって,G1W の著作権の有無やその帰趨は,G1X MS-DOS 版の著作権の所在に影響するものではない。 また,Aは,G1W のソースプログラムを橘高工学に渡していないから,橘高工学が G1W を翻案することはもとより,デッドコピー以外の複製をすることも困難である。他方,Aは,G1W のソースプログラムを管理しているから,複製・翻案は自由にすることができる。このことからすれば,Aが G1W の著作権を橘高工学に譲渡したと認めることはできない。 eよって,被告の主張は採用することができない。 (イ)職務著作に該当するとの主張について被告は,橘高工学とAとの関係は,実質的には,橘高工学の指揮監督下においてAが労務を提供するという実態にあり,橘高工学がAに対して支払う金銭は労務提供の対価と評価できるので,G1X MS-DOS 版は,いずれも橘高工学の発意に基づき作成されたプログラムであって,職務著作として,橘高工学が著作者であると主張する。 著作権法15条2項は,「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。」と規定する。そして,「法人等の業務に従事する者」とは,法人等との雇用関係の存否が争われた場合であっても,法人等と著作物を作成した者との関係を実質的にみたときに,法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり,法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを,業務態様,指揮監督の有無,対価の額及び支払方法などに関する具体的事情を総合的に考慮して,判断すべきものである(最高裁平成15年4月11日第二小法廷判決・集民209号469頁参照)。 本件においては,Aが G1X MS-DOS 版を開発したのは橘高工学の依頼によるものであるが,Aと橘高工学との間に雇用関係はなく,前述のとおり,橘高工学が G1X MS-DOS 版をそれぞれ発注した時に,具体的にどのような技術的指示をしたか被告は明らかにしていない。むしろ,前記認定のとおり,橘高工学が,GDX 等の開発をAに依頼した際,プログラムの画面デザインの1つ(主要画面)を示され,それ以外の画面(15枚)の設計及びそれに見合う機能を持つプログラムはAが自己の裁量で開発し,橘高工学の従業員から,プログラムのデザイン,機能,操作等に関するアドバイスは受けなかったことが認められる。 また,Aは,GDX 等については,注文書(甲30)により発注を受け,GPS 装置付きグラブ浚渫施工管理システムに対応するプログラムの初期版(GNX)についても,それに対応すると思われる納品書(甲40の24枚目)が発行され,報酬が支払われている。このように,Aと橘高工学の関係は,Aが労務を提供して,橘高工学がその対価を支払うというよりは,橘高工学がAに仕事の完成を依頼し,その仕事の結果に対して報酬を支払うというものであった。 したがって,Aは,G1X MS-DOS 版の開発に際して,橘高工学の指揮監督の下で労務を提供し,その対価を受けたと認めることはできないから,G1X MS-DOS 版が職務著作としてその著作権が橘高工学に帰属することはない。 (ウ)橘高工学から被告への譲渡被告は,橘高工学破産管財人が平成13年3月に被告に対して,橘高工学が有していたサーバを動産一式に含まれるものとして譲渡した際,同サーバにはプログラム(G1X MS-DOS 版を含む。)が保存されていたので,プログラム著作権も売買の目的物として被告に移転していると主張する。 しかし,前記のとおり,動産であるサーバが譲渡されたからといって,その中に保存されていたプログラムについて,著作権も譲渡されたことになるものではないから,被告の主張は失当である。 (2)船体位置決めプログラムの著作権の帰属船体位置決めプログラム NB 版はAが作成したものであり,船体位置決めプログラムは,A(のちに原告に譲渡)ないし橘高工学に帰属すると考えられるところ,橘高工学から著作権が譲渡されたことはないので,船体位置決めプログラムの著作権は,少なくとも被告には帰属しない。 5本件プログラムの創作性の有無(前記第4の1(1)の争点)について(1)OS 及び言語の変更ア原告は,本件プログラムは,G1X MS-DOS 版とは,OS が MS-DOS と Windowsとで異なり,プログラム言語も C 言語と VisualC++とで異なるので,創作性が認められると主張する。 イ確かに,言語の著作物の場合,著作物を言語体系の異なる他の国語で表現して「翻訳」したのものは「二次的著作物」であるとされている(著作権法2条1項11号)。 しかしながら,前述のとおり,プログラムの表現は,所定のプログラム言語,規約及び解法による制約がある上に,その個性を表現できる範囲は,コンピュータに対する指令の表現方法,その指令の表現の組合せ及び表現順序というように,制約の多いものである。したがって,あるプログラムの著作物について,OS やプログラム言語を異なるものに変換したからといって,直ちに創作性があるということはできず,OS や言語を変換することにより,新たな創作性が付加されたか否かをを判断すべきである。 ウ本件では,原告は,OS 及び言語を変更したことによって,どのような創作性が付加されたかについて具体的に主張立証していない。本件プログラムのソースプログラムの文字数は,G1X MS-DOS 版の5倍以上に増加しているが,その多くは,言語を変更したことによるというよりは,主として新たな機能を追加したことによるものである可能性もある(平成17年8月19日付け原告の第5回準備書面17ページ参照)。このことに加えて,VisualC++はC言語に対して基本的には上位互換性を有する(C言語のモジュールをコピーして使用することもできる)と認められること(弁論の全趣旨),G1Xver5.50 のソースプログラムの一部(モジュール)である「G1xLan.cpp」(乙18),「g1x.h」(乙19)に平成9年5月のGによるコメントの追加があるように,平成9年以前すなわち G1XMS-DOS 版の記述がそのまま用いられている部分があることに照らせば,本件プログラムが,MS-DOS・C 言語から Windows・VisualC++へと OS 及びプログラム言語を変更させたことのみによって,創作性があるものとまで認めることはできない。 (2)追加機能 3)の RTM に相当する部分の関数についてア証拠等(各事実の末尾に記載)によると次の事実が認められる。 (ア)RTM の機能は,DOS エラー処理,初期処理,終了処理,タイマー割込処理,再起動処理,ファンクションキー処理,タスク生成処理,タスク実行処理,タスク切替処理,タスク停止処理,メッセージ送受信処理,スタック初期処理,タスク初期処理,タイマー開始・停止処理,キー入力処理,画面出力処理,画面スクロール処理,漢字入力制御処理,ハードコピー処理,セマフォー制御処理,システムタスク処理,デバッグタスク処理,タイマータスク処理,スプールタスク処理,ハードコピータスク処理,メニュー処理,印刷処理,EMS メモリー処理である。(甲14)(イ)MS-DOS は,シングルタスク OS(複数のタスクを同時に実行できず,複数のタスクをタイムスライスに応じてディスパッチすることができず,一度に1つの処理のみ実行できる。)で,その機能は,データのやりとり管理,周辺機器の制御,ファイル管理である。グラブ浚渫施工管理システムでは,複数の入力装置(位置計測装置,重機制御装置,潮位計,船体傾斜計等)からのデータが非同期に発生するが,シングルタスク OS では,ポーリング手法(通信機器やソフトウェアが複数で関連して動作する場合に,送信や処理の要求がないか,逐一巡回して確認する方式)を用いるため,1つのデータ処理を行っている間は,他のデータ処理が実行できず,他のタスクがサービスを待機している間にデータの取りこぼしなどが生じないようにプログラミングをする必要がある。 他方,マルチタスク(1台のコンピュータで同時に複数の処理を行うOS の機能)及びタイムシェアリング(1台のコンピュータの CPU の処理時間をユーザ単位に分割することにより,複数のユーザが同時にコンピュータを利用できるようにすること。)があれば,複数のデータの処理タスクは,それぞれ毎秒最低でも10回程度のサービス時間が与えられ,システムの応答は格段に向上する。 RTM はマルチタスク及びタイムシェアリングの機能をさせるために開発された。(以上につき甲44)(ウ)G1X MS-DOS 版には RTM が用いられていたが,RTM は Windows には対応しておらず,本件プログラムに RTM は用いられていない。(争いがない。)(エ)G1X MS-DOS 版では RTM が機能していたマンマシン・インターフェース部分について,RTM を用いない場合にどのようなプログラムとするかについては,Ⅰ)関数を使用するか,Ⅱ)関数を使用する場合,どのような関数を使用するか,Ⅲ)それによってどの程度のプログラムが必要となるか,といった事柄について選択肢があるため,プログラマーの個性が表れる余地がある。(甲46)(オ)G1Xver3.00 の G1x.cpp(甲36の3番号5)には,別紙6のとおり,①******************) 」以下の部分(甲36の3番号5の9ページ40行目から10ページ3行目まで),②「******************」以下の部分(同10ページ4行目から32行目まで),③「******************」以下の部分(同10ページ33行目以下)のような記述がある(G1Xver5.50 についても乙47の1の6の10,11ページにも同様の記載がある)。G1X MS-DOS版では RTM が機能していたマンマシン・インターフェース部分については,上記記述部分の関数が担っている(甲45)。 (カ)上記部分のうち②,③にそれぞれある「*****」に対応して「*****」が13列並んでいる部分は,記憶させるデータのタイプを13分類して,そのタイプを指定することにより,画面からの入出力が共通のルーチンとして使用できるもので,これにより,画面でいろいろな項目に対して,標準化してタイプごとに処理することが可能となり,迅速かつ正確なプログラムを組むことが可能となる。(甲46)(キ)上記の13列の部分は,Aが独自に創作した部分であり,他のプログラマーが同様の機能をもつプログラムを開発するとすれば,それよりは冗長なものになる可能性が高い。(甲46)イ以上に認定した事実からすれば,本件プログラムにおいて,G1X MS-DOS 版では RTM がその機能を担っていたマンマシン・インターフェースを担う部分については,同部分がなければ本件プログラム自体がまったく機能しないというものではないが,同部分があることによりプログラムの処理が円滑に行われるというものであって,同部分を設けるか,設けるとした場合に同部分をどのようなプログラムとするのか,その場合の関数の使用の有無・内容,プログラムの量等について,様々な選択肢があり,プログラマーの個性を発揮することが可能であるところ,本件プログラムにおいては,Aは,記憶させるデータのタイプを13分類して,そのタイプを指定することにより,画面からの入出力が共通のルーチンとして使用するという,「******」から始まる列を13列並べるという独特の表現をしており,同部分については,Aの工夫が凝らされていてその個性が認められるから,著作物性を有する。 ウ被告は,原告の主張する関数は,RTM を用いる前から用いられていたもので,Windows に対応するように記述したからといって創作性が生じるものではないと主張する。 具体的には,平成4年に作成されたグラブ浚渫施工管理システムのプログラム GDT(RTM が用いられる前のもの)に「********」という関数が用いられているが,G1Xver3.00 の「G1xship.h」(甲36の2番号21)には「**********************」という関数が用いられ,両者は同じ思想によるものである,G1Xver3.00 の「G1x.cpp」(甲36の3番号5)には「*****************」「********************」の関数が用いられているが,これは RTMを用いる前から用いられていたと主張する。 しかしながら,例えば,G1X ver2.00 の「G1X」というモジュール(乙46の1の1)には,上記の「******」が13列並んでいる部分と同様の表現はなく,その他にも同表現が,本件前プログラムに存在したと認めるに足りる証拠はない。したがって,「******」が13列並んでいる部分の表現は,本件前プログラムにはなかった新しい部分であるし,単にWindows に対応するように機械的に記述したにすぎないと認めるに足りる証拠はないから,被告の主張は理由がない。 (3)新可能処理②の鳥瞰図表示についてア証拠等(各事実の末尾に記載)によると次の事実が認められる。 (ア)本件プログラムにおける鳥瞰図表示は,メイン画面において,浚渫作業の程度・状況及び水底の凹凸起伏の程度・状況について,ソナー装置により水面から水底までの深度を計測し,同データに基づいて,水底の各地点の計測座標ごとに,計測した深度別に異なる色に塗り分け,かつ計測した深度に基づいて水底の凹凸起伏の高低が立体的に見えるように表示するものである。同画面においては,領域の移動,視点の移動,拡大・縮小が可能であり,マウスカーソルを鳥瞰図の描画箇所に移動させれば,その箇所の座標と深度が表示される。(甲45,乙50)ソナー装置は,水面から水底までの深度を計測する装置であり,水面下1メートル程度の位置に沈め,高周波のパルスが与えられた圧電素子が発する超音波が海底に反射しエコーとして帰ってくる時間を計り,距離を算出する装置で,グラブ浚渫船では設置されているのは10パーセント以下である。浚渫作業のバケットが掘った水底の深度も,バケットが水面上にある時間帯を利用してソナー装置により計測することができる。(甲49)ソナー装置がない場合又は水中の濁りが多い等によりソナー装置を使用することができない場合は,甲板員が,竿の先に目盛と着底が分かる錘を付けたロープを作業船上から水底に向けて垂らして,手動で深度を測定する。ソナー装置を使用しない場合は,バケットの深度と位置の情報,バケットが開いたときの1堀で浚渫できる最大の平面的な範囲等をソナー計測によるデータに例えて,擬似的に1メートルピッチの密度による深度データを計算して,鳥瞰図を作成する。(甲49)(イ)鳥瞰図の作成の機能は,本件前プログラムにはなく,本件プログラムすなわち G1Xver3.00 以降のものについて新しく付加された部分である。 (争いがない。)(ウ)本件プログラムにおける鳥瞰図を作図させる機能の部分は,「G1xChokan.cpp」(G1Xver3.00 では甲36の3番号7,G1Xver5.50 では乙47の1の10)及び「G1xChokan.h」(ヘッダーファイル)である。 そのプログラムのサイズは,G1Xver3.00 で「G1xChokan.cpp」が13キロバ イ ト , 「 G1xChokan.h」 が 3 キ ロ バ イ ト , G1Xver5.60 で「G1xChokan.cpp」が1万3113バイト,「G1cChokan.h」が2177バイトである。 なお,G1Xver5.60 のソースプログラムは,ヘッダーも含めて全体で116万3074バイトであり,うち「resource」が77万9242バイトで あ り , そ れ 以 外 の 部 分 の 合 計 は 3 8 万 3 8 3 2 バ イ ト で,「G1xChokan」は,30あるモジュールのうち5番目に大きいサイズのものである。(甲11,13,24,38,45)(エ)「G1xChokan.cpp」は,ソナー装置のデータから鳥瞰図を表示し,ソナー装置のデータを取得できない場合に,施工実績データから鳥瞰図を擬似的に表示するための処理を行うものである。 (オ)「G1xChokan.cpp」では,3次元から2次元平面に投射するロジックについて行列式でコメントが記述されているが,プログラムの表現としては,行列式の1個の要素に数字を代入し,行列式の計算を四則演算に分解する記述がされている(甲36の3番号3の5ページ40行目以下,乙47の1の10の5ページ13行目以下)。 イ以上に認定した事実からすれば,本件プログラムにおける鳥瞰図の表示は,Ⅰ)ソナー装置がある場合はソナー装置により計測した水底の起伏状況についての位置(座標),深度の3次元データ,グラブバケットの位置・深度データを収集し,Ⅱ)ソナー装置を用いない場合は,位置決めシステムによる位置情報,手動で計測した深度情報,バケットの1堀の範囲等から計算したデータ等を集積して,ソナー装置の計測によるデータに例えて1メートルピッチの密度による深度データを計算し,位置・深度の3次元データを収集し,Ⅲ)収集した3次元データを2次元平面に投射する処理をし,Ⅳ)これを特定のデザイン,大きさ,縮尺,色彩を持った画像に置き換える処理をするという手順を踏むものであることが認められる。 そして,上記のいくつかの段階を踏む処理について,「G1xChokan.cpp」は1万3113バイトの容量(「resource」を除いたモジュールの合計容量の約4パーセントで,30あるモジュールのうち5番目に大きい容量)を用いて記述されていることからすれば,その処理に至る手順,方法に関する表現について選択の余地があり,また,デザイン,大きさ,縮尺,色彩に様々な選択肢がある以上,これを表示するための演算処理等の記述についても,様々な表現が選択可能であり,「G1xChokan.h」及び「G1xChokan.cpp」は,それら中から特定の表現を選択したものと認められる。 したがって,本件プログラムにおいては,その記述ないし表現についてAの個性が現われていると認められるから,本件プログラムの鳥瞰図表示の部分は著作物性を有するものというべきである。 ウ被告は,鳥瞰図の画面表示は極めてありふれており,視点を移動できる点も,平行移動,回転に行列計算が用いられているが,数学上当然のものであり,プログラムとしては目新しいものではない,陰線処理はZバッファ法というありふれた方法が用いられているとして,創作性を否定する。 しかし,被告がありふれていると指摘するのは,プログラムの表現それ自体ではなく,画面表示や,陰線処理の方法についてのものにすぎない上に,当時,本件プログラムで表される画面表示や陰線処理の方法がありふれていたものであるとの立証はない。また,同部分の処理及びその他の部分の処理をするプログラムの表現について,G1xChokan.cpp(甲36の3番号7,乙47の1の10)を前提としても,具体的にどの表現がどうありふれているかについての具体的な指摘や主張立証はない。 被告は,視点を移動できる点についても,行列計算が用いられているのは数学上当然であると主張するが,G1xChokan.cpp を前提として本件プログラムで用いられている行列計算等の表現それ自体がありふれていることについての指摘,主張立証はない。 (4)まとめ本件プログラムにおいては,OS とプログラム言語の変更による創作性の立証があるとはいえないものの,少なくとも,RTM に相当する部分の関数と鳥瞰図表示の部分のプログラムについては,その表現に作成者Aの個性が現れており,著作物性があるものと認められる。よって,本件プログラムは,少なくとも G1X MS-DOS 版の二次的著作物として,少なくとも上記の著作物性が認められる範囲で,著作物として保護される。 6本件プログラムの著作権の帰属(前記第4の1(2)の争点)について(1)G1Xver3.00 の開発経緯前記2で認定した事実及び前記第3の前提となる事実により認められるG1Xver3.00 の開発経緯及び事情についてまとめると,次のとおりである。 すなわち橘高工学は,平成12年1月,G1Xver3.00 の開発をAに発注したが,同開発契約においては,同プログラムの著作権の帰属に関する明示の文書はなかった。また,開発内容としては,第16堀松号に設置するソナー計測装置に対応し,Windows 対応のものという限定があったのみで,プログラム言語の指定はなく,Aの独断で VisualC++により開発した。 そして,G1Xver3.00 は,同年4月ころ,ソースプログラムが作成され,コンパイルされて,オブジェクトプログラムがいったん NAV-LAH Ⅲの GPS 受信装置にインストールされて第16堀松号に設置されたが,ソナー計測装置の不具合の関係で調整が必要となったため,いったん作業は中止となり,その間,橘高工学が破産宣告を受けた。その後,第16堀松号のソナー計測装置の調整が終わり,Aは,SKKからの依頼で,G1Xver3.00 のオブジェクトプログラムをインストールし,デバッグ等の調整を終えて,同年7月に作業を終了した。 その結果,橘高工学は,G1Xver3.00 のソースプログラムをAから受領することもなく破産手続に入り,破産宣告後に橘高工学から第三者に対して何らかの著作権が譲渡されたことはない。 Aは,G1Xver3.00 に関する費用や対価として,橘高工学に対して500万円を請求する予定であったが,結局橘高工学からは何も受領することができず,SKKから開発費及び現地調整費として335万円の支払を受けた。 な お , A は , G1xver3.00 の 「 G1x の バ ー ジ ョ ン 情 報 」 の 画 面 に は「(c)Copyright Nihon System Plannnig 2000 All Rights Reserved」の表示が現れるようにソースプログラムに記述をし,堀松建設以外に,平成12年8月ころ,日本測器経由で,大潮建設に G1Xver3.00 の複製物を販売している。新洋海工の36龍王丸にも,橘高工学ないし被告を通すことなく,G1X の Windows版(本件プログラムと思われる。)を納品し,後に被告設立後にBから苦情を言われている(弁論の全趣旨・原告の平成17年12月8日付け第10回準備書面9ページ)。 (2)本件プログラムの著作権の帰属上記のとおり,G1Xver3.00 は,Aが,G1XMS-DOS 版に新たな創作性を付加して創作した著作物であり,少なくとも G1X MS-DOS 版の二次的著作物ということができる。そして,Aから,橘高工学ないし被告に著作権が譲渡されたと認めるに足りる証拠はない。かえって,橘高工学は,Aに対し,著作権の譲渡代金と評価できる対価はもとより,開発費の支払もせず,ソースプログラムも渡されず,Aのみがソースプログラムを保有し,Aは,橘高工学破産宣告後に別の業者を通じてプログラムの複製物を販売して,橘高工学以外の業者から報酬を得ており,プログラムにAの屋号である「Nihon System Plannnig」の著作権表示が現れるようにして,自己の著作権を主張しているから,G1Xver3.00の著作権は,その著作者であるAに帰属していたと認められる。 次に,G1Xver5.24 ないし G1Xver5.70 は,被告から依頼を受けて,AがG1Xver3.00 をバージョンアップしたものであるが,そのソースプログラムはAのみが保有・管理し,被告は保有しておらず,Aは,G1Xver5.24 ないしG1Xver5.70 の各バージョン表示メニュー画面に「Nihon System Plannnig」の著作権表示が現れるようにして著作権の主張をしていることからすれば,本件プログラムは,G1Xver5.24 ないし G1Xver5.70 にバージョンアップされた後も,引き続きAに著作権が帰属しており,被告に譲渡されることはなかったものと認められる。 そして,Aは,平成15年8月までに,本件プログラムの著作権を原告に譲渡しているので,本件プログラムの著作権は原告に帰属する。 (3)被告の主張についてアソースプログラムの保有・管理被告は,原告ないしAに対し,専属的にバージョンアップ等を依頼していたので,ソースプログラムは必要なかったから保有していないと主張する。 しかし,橘高工学は,従前,Aにソースプログラムの提出させていた。このこととの比較で考えると,バージョンアップを依頼しているからといって,ソースプログラムが必要ないということはできない。むしろ,被告がソースプログラムを原告ないしAに提出させていないのは,被告が,ソースプログラムの提出を要求できる立場になかった(橘高工学のように「橘高工学が依頼してAが作成したプログラムはもともと橘高工学に帰属するから,ソースプログラムを提出するのは当り前である」と主張することもできなかった)ものであり,著作権に関して,橘高工学よりも更に弱い立場にあったこと(もっとも,デッドコピーについては許諾ないし黙認されていた可能性がある。)を示すように思われるところである。 イ対価の支払被告は,橘高工学が G1Xver3.00 を発注した平成12年1月に,Aに対し,本件手形①②を振り出して仮払をし,Aは少なくとも本件手形①の手形金170万円から「バック」分を除いた121万円は受領しているし,本件手形③ないし⑥についても,「バック」分を除いた合計245万円は,不渡りになっていなければAに支払われるものであり,橘高工学の破産により履行されなかったにすぎないと主張する。 しかしながら,当時,Aは,橘高工学から複数のプログラムの開発・改良の仕事を依頼されてその対価が未払であり(例えば「本間組向け捨石均しシステム」の現地調整費,「フジタ向け水中打設システム」の開発費,KSCオシロソフト」の修正費は,平成12年5月時点で未払であった。甲40の79,80,85枚目,甲44,乙55の8。その項目と金額が確認できる甲40の79,80,85枚目は,他の甲40の納品書等とは異なり,Bの指示で項目を記載したのではなく,A自身の判断で当時未払であったものについて記載したものである。原告代表者18ページ),G1Xver3.00 の発注を受けた日にも「本間組深浅測量+ソナー」についての打合せもしており(乙55の11),「仮払」として支払われた121万円がいずれの発注についての対価であるか不明である上に,前記2で認定したとおり,AがBの指示により記載していた請求書等(甲40)の項目も,全般的に実際の明細(乙55,58添付別表)とは異なっていて,「仮払」の121万円がいずれの項目に対する支払であるかをAが特定して認識していたとは認められない。 また,前認定のとおり,G1Xver3.00 のプログラムの複製物を納品した相手方であるSKKからは,その対価として300万円(この金額はAとしては値引きされたものである。甲44)がAに支払われている。このことからすれば,仮に121万円が G1Xver3.00 の開発費として支払われたものであったとしても,ブログラムの複製物1本分の対価にも満たないものであって,この支払により G1Xver3.00 の著作権が移転するとは認められない。なお,仮に,上記245万円が,G1Xver3.00 の開発費に含まれるものであったとしても,現実に支払われていない以上,これを G1Xver3.00 の著作権の移転に影響を与えるものとすることはできない。 ウ各人の行動・認識,システム全体におけるプログラムの位置づけ被告は,本件プログラムは,橘高工学が開発したグラブ浚渫施工管理システム専用のプログラムで,複製して同システムにインストールして,これらを多数販売することを目的としたもので,その後のバージョンアップも予定しているものであるから,複製の都度,Aに許諾料を支払うつもりで依頼したとは考えられない,また,本件プログラムは,グラブ浚渫施工管理システム全体において占める割合は小さく,システム自体は橘高工学が開発したものであると主張する。 しかし,前認定のとおり,G1Xver3.00 あるいは本件前プログラムはまったく汎用性がないものではない。また,橘高工学が,G1Xver3.00 の複製物の販売を予定していたとしても,Aが橘高工学に包括的にプログラムの複製を許諾し,開発費に複製許諾料も含めて対価を支払うことも可能であるし,バージョンアップについては,著作権法20条2項3号の範囲を超える改変が見込まれる場合は,同一性保持権の放棄あるいは包括的に翻案を許諾することも可能であるから,橘高工学が G1Xver3.00 の複製販売を多数予定しバージョンアップを予定していたことのみをもって,Aから橘高工学へ同プログラムの著作権の譲渡の合意があったと認めることはできない。 なお,被告は,Aないし原告が,平成16年4月まで本件プログラムの著作権者である旨の主張はしなかったと主張する。しかし,前認定のとおり,Aないし原告は,本件プログラムの画面のバージョン情報等に日本システムプランニングの著作権表示をしており,ソースプログラムを独占管理しつつ,「ソフト代」「バージョンアップ費」等の名目で被告から金員を受領しているから,敢えて著作権に基づく何らかの請求をする必要がなかったと考えれば,その行動が特に不合理であるとはいえない。被告の指摘する上記事実は,A及びその後の原告の著作権の帰属を否定するものとはならない。 エ著作権表示(ア)取扱説明書に記載の画面の著作権表示被告は,G1Xver3.00 の取扱説明書(乙50)の起動時画面及びバージョン情報画面に「(c)Copyright by Kittaka Engineering LaboratoryCo.,ltd 2000 All Right reserved」があり,これはA自身が記載したものであると主張する。 確かに,Aは,平成12年4月の段階では,上記のとおり,橘高工学の著作権表示をしたことが認められるが,その後,著作権表示を日本システムプランニング名義のものに変更している(乙42)。しかも,Aは,橘高工学にソースプログラムを交付していないから,橘高工学はG1Xver3.00 を修正することができないのに対し,Aは自由に修正(複製の範囲内の修正や翻案)ができる。上記事実に照らせば,Aによる上記の橘高工学の著作権表示は,G1Xver3.00 の著作権がAから橘高工学に譲渡されてはいないとの上記認定を覆すに足りるものではない。 なお,Aは,G1Xver3.00 の取扱説明書(乙50)の起動時画面及びバージョン情報画面に「(c)Copyright by Kittaka Engineering LaboratoryCo.,ltd 2000 All Right reserved」を記載した時点では,それが完成して十分な対価が支払われたあかつきには,橘高工学が G1Xver3.00 という特定のバージョンについて,対外的に著作権があるように振る舞うことを許容する意思があった可能性もなくはない。しかし,結局,橘高工学からは対価が支払われず,Aは,橘高工学にソースプログラムも交付せず,著作権表示を日本システムプランニング名義のものに変更し,自らSKKにプログラムの複製物を納品するなど,橘高工学を無視して著作権者として振る舞っている。このことからすれば,仮に,完成して十分な対価が支払われたあかつきには,橘高工学が G1Xver3.00 という特定のバージョンについて,対外的に著作権があるように振る舞うことを許容するという意思がAにあったとしても,それは対価の支払を受けた後の予定に止まり,橘高工学からの対価支払がないために実現しなかったもののように思われる。 したがって,上記可能性も,上記認定を左右するものではない。 (イ)モジュール「CalhaVa.cpp」の著作権表示被告は,G1Xver5.50 のソースプログラムのモジュール「CalhaVa.cpp」のトップには平成12年2月1日付けで橘高工学の著作権表示が現れるので,G1Xver3.00 の4月版及び7月版にも橘高工学の著作権表示のある「CalhaVa.cpp」が入っているはずであると主張する。 確かに,G1Xver5.50 のソースプログラムのモジュール「CalhaVa.cpp」のトップには橘高工学の著作権表示が現れる(乙47の2の1)。これに対し,原告は,同モジュールは,実際の船体傾斜の位置補正ルーチンを内容とし,G1Xver3.00 のモジュール「G1x.cpp」の「RotZpr」「RotPr」をもとに作成した社外説明のためのソナー制御装置のプログラミング用のもので,G1Xver3.00 の一部ではなく,本来 G1Xver3.00 に不必要なものであると主張する。 証拠(乙47の2の1)によれば,「CalhaVa.cpp」には「****************」のプログラムであることや,Input,Output,Retuern や「****************」等の説明が日本語で冒頭に記載され,G1Xver3.00 のモジュールとは体裁が異なることが認められる。また,原告が「CalhaVa.cpp」のモジュールの問題を指摘した平成18年3月ころ(被告第9準備書面)より前である平成17年10月31日の第2回弁論準備手続期日で提出された本件プログラムのモジュール一覧表(甲11)にも「CalhaVa.cpp」の記載はない。さらに,たった1つのモジュール「CalhaVa.cpp」にだけ,全体とは異なる著作権表示がされるというのも不自然である。 以上の点からみれば,これが G1Xver3.00 の一部ではなく,社外用の説明のために作成したモジュールであるとの原告の主張も,肯認することができる。そして,社外用の説明のために作成したモジュールであれば,橘高工学が販売するシステムにインストールされるプログラムであることから,対外的に橘高工学の著作権表示を入れていたとしても不自然ではない。 よって,「CalhaVa.cpp」において橘高工学の著作権表示があることは,前記のAに G1Xver3.00 の著作権が帰属するとの認定を覆すものとはならない。 7著作権の権利主張についての対抗要件の要否(前記第4の1(5)の争点)について被告は,原告が著作権移転のための対抗要件である登録をしていないので,被告に対し,著作権を有していることを対抗できないと主張する。 しかし,著作権の移転を登録しなければ対抗できない「第三者」(著作権法77条)とは,登録の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する者であると解されており(大審院昭和7年5月27日判決・民集11巻11号1069頁参照),単なる著作権の侵害者はこれにはあたらない。よって被告の主張は失当である。 8差止請求の可否(前記第4の1(6)の争点)について被告は,現在,G1Xver5.24 ないし G1Xver5.70 をグラブ浚渫施工管理システムに使用していないと主張するが,過去に別紙1のとおり,本件プログラムの複製物を販売しているので,著作権を侵害するおそれは認められる。 9損害論(前記第4の1(7)及び(8)の争点)について(1)被告の著作権侵害についての故意・過失の有無被告は,G1Xver3.00 の著作権がAに帰属していたとしても,Aが自ら,G1Xver3.00 のトップページに橘高工学の著作権表示をしている以上,被告が橘高工学に帰属していたと認識していたことについて過失はないと主張する。 しかし,前記のとおり,平成12年4月時点では,G1Xver3.00 のトップページに橘高工学の著作権表示があったが,その後,Aは,G1Xver3.00 について,著作権表示を日本システムプランニングに書き直しているし,G1Xver5.24以降については,当初から日本システムプランニングの著作権表示を記載している。 そして,被告が複製物を販売したプログラムに,日本システムプランニング(原告ないしA)の著作権表示がある以上,過去にこれと異なる著作権表示のある時期が一時的にあったとしても,現に著作権表示をしている者に対する問い合わせ等,著作権の帰属について十分な注意を払うべきであり,被告にはこれを怠った過失がある。 したがって,被告には,本件プログラム及び G1X MS-DOS 版の各著作権を侵害することについて過失があったということができる。 (2)損害発生の有無及びその数額ア被告が別紙1のとおり,本件プログラムを複製販売したことは争いがない。 被告による上記の本件プログラムの同複製販売は,原告ないしAの本件プログラムの著作権(複製権)を侵害するので,被告は,原告ないしAに対し,その損害を賠償する責任を負う。なお,Aの損害賠償債権は原告に譲渡されている。 イ前記のとおり,被告が,Aないし原告に対し,G1X 関係のプログラムの修正・改造の依頼に際して支払ってきた報酬の金額は,別紙5のとおりであり,50万円ないし80万円であるが,これには,①プログラムの修正・改造(主として,MS-DOS 版を使用していた作業船について Windows 版のプログラムに変更するバージョンアップの作業。原告代表者61,62ページ)の費用(作業をした場合),②橘高工学時代の損害の填補(作業がなかった場合もしくは作業料を差し引いた剰余がある場合)が含まれている。したがって,50万円全額がプログラムの複製の許諾料であると認めることはできない。原告自身も,50万円の支払について,実際に仕事をしなかった場合もあるが,仕事をした場合もあることを認めている。 ウ別紙5において,平成13年1月から平成15年10月までで「調整」「修正」「改造」の費用として支払ってきたもの(一部未払のものも含む。)は,次のとおりである(消費税抜き)。 福丸建設調整費30万円(平成13年8月1日)てんゆう修正10万円(平成14年4月1日)豊号修正40万円(平成14年4月1日)森長組改造費20万円(平成15年3月25日)福丸改造30万円(平成15年10月10日)エ前記のとおり,橘高工学が,Aに対し,G1X 関係のプログラムの修正・改造の依頼に際して支払ってきた報酬の金額は,別紙4のとおりであり,「調査」「実験」「立会」「ソフト変更」の費用として支払ってきたことが明らかなものは,次のとおりである(消費税抜き)。 4つの客先への現地調査費10日分70万円(平成10年5月)本間組(9/23 実施分)15万円(平成10年10月)本間組実験(11月分前倒し)15万円(平成10年10月)18昭和(実験3日)15万円(平成11年4月)葵建設(ソナー立会3日)20万円(平成11年4月)青木組向けソフト変更20万円(平成11年12月)オ原告が提出した納品書等(甲40)に記載されている金額のうち,その項目が「改修」「修正」「立会」等となっているものは次のとおりである(消費税抜き。ただし,前述のとおり,実際の支払金額及び項目とは一致していない。)。 KSCNEW ソフト修正20万円(平成8年9月20日)グラブ浚渫 GSX 改修50万円(平成8年11月20日)山本建設工業ソナー立会費20万円(平成9年2月20日)太平工業仁川向けソフト改造215万円(平成9年2月20日)国総向け KSC ソフト改造100万円(平成9年3月20日)大新土木向客先仕様追加100万円(平成9年4月20日)G1Xver1.1 吃水計追加40万円(平成9年4月20日)国総向け KSC 修正7万5000円(平成9年5月20日)国総向け KSG オシロソフト修正費50万円(平成12年5月20日)カまた,原告は,平成18年1月26日付け第11回準備書面8ページにおいて,「当時から,橘高工学と原告代表者との間に正式な書面契約は,締結されておらず,その間に「グラブ浚渫施工管理システムソフト G1X」が,年間20セット以上,出荷の有った時期が有った。橘高工学としては,その頃,かなりの利益が上がった筈で,その当該ソフト作成者で有る,原告代表者に対する支払いも,この利益配分としてのライセンス料と原告代表者は,勿論被告自身も十分,認識していたはずで有る。しかし,原告代表者は,ライセンス料と言う名目にこだわらず,被告に頼まれたソフトバージョンアップ費用や修正料の名目で,作業ごとに1件当たり,20万円程度から30万円程度の請求を行って来た。又,橘高工学は,外注費として支払った費用の数倍のソフト販売利益を当然ながら得ていた筈である」と述べており,①作業船ごとの調整作業の費用に②ライセンス料を加えた金額は,1件あたり20万円ないし30万円が相当である旨述べている。 キ上記の事実からすれば,改造,修正,調査,立会等の費用としては,個別の案件によって異なるのは当然であるが,100万円を超えるような特に大きな金額のものを除くと,おおよそ20万円ないし30万円の範囲にあるとうことができる(なお,Aの認識では,G1X MS-DOS 版の時代では複製許諾料を含めても20万円ないし30万円となる。)。 クまた,平成13年1月から平成15年10月までに支払われた各50万円ないし80万円については,上記の実費報酬金額を差し引いた金額について,被告はA(原告)に,仕事の対価としてではなく支払を続けていた。 これを客観的にみれば,被告は,G1X 関係のプログラムを販売できた時に,その利益の一部を,損失補填のためにA(原告)に支払っていたということができる。そして,その損失補填額の上限が決められていたわけでもなく,被告は,支払を終わらせると言えば,Aないし原告は他の理由等で金銭の要求をすることが予想され,Aないし原告にソースプログラムを独占管理されていることからやむなく支払を継続したというのであるから,そのままではずっと支払の継続を強いられることになりかねない。 そして,この状態は,Aないし原告(著作権者)がソースプログラムを独占管理しているために,被告はプログラムの複製物を販売した利益の一部を著作権者に支払うことを強いられている状態ということができるから,外形的にはプログラムのライセンス料とみる余地もないではない。すなわち,A(原告)がプログラムの複製許諾料を要求した場合,ソースプログラムを独占管理されている関係上,被告は要求に応じざるを得ないところ,当面は,被告がプログラムの複製物を販売した利益の一部を任意に支払ってくる(損失補償してくる)ので,A(原告)は「ライセンス料」名目での金銭支払要求をせずにライセンスをしているものの,被告が「損失補償」の支払を終了させると主張した場合には,A(原告)は他の理由(ライセンス料名目)で金銭を要求するであろうから,上記「損失補償」はライセンス料の変形にすぎないとみる余地もあるのである。 しかし,この支払は,支払額を被告がその都度決定していたものであるから,定額の許諾料が決められていたとすることはできず,損失填補の趣旨で上記のように外形的にはライセンス料とみる余地のある支払がされたことがあるという意味で考慮するに止めるべきである。 ケ本件プログラムは,G1X MS-DOS 版の二次的著作物であるところ,仮に,G1X MS-DOS 版が船体位置決めプログラムを原著作物とする二次的著作物であり,船体位置決めプログラムの原著作権が原告にあったとしても,G1XMS-DOS 版は,船体位置決めプログラムと較べて大きな追加や変更がなされ,その後 G1X MS-DOS 版の時代にもモジュールが多数追加され,更に,本件プログラムでも創作性のある部分の追加がされているため,本件プログラムは船体位置決めプログラムよりも,サイズもはるかに大きく,内容も異なるものとなっているものであるから,本件プログラムの経済的価値について,船体位置決めプログラムの創作性のある部分の与える影響は,ごく小さなものとなっているというべきである。 コ本件プログラムのうち,少なくとも創作性があると認定した RTM に相当する部分の関数と鳥瞰図表示の部分のプログラム以外の部分については,創作性が認められる余地がないとはいえないが,その表現により処理される機能が比較的ありふれたものであることからすれば,本件プログラムの経済的価値の評価に当たって特段の考慮をしなければならないものとまでは認められない。 サ以上の事実を斟酌すれば,本件プログラムの著作権侵害により請求できる損害金は,1つの複製につき35万円と認めるのが相当である。したがって,別紙1のとおりの合計20の複製行為により請求できる損害金は,合計700万円である(原告は消費税相当額は請求していない。)。 (3)原告の主張についてア原告は,Aと被告との間で,1つの複製につき許諾料50万円を支払う旨の複製許諾契約が成立していたので,1つの複製についての許諾料相当損害金は50万円であると主張する。 しかし,1つの複製につき許諾料を50万円という定額での複製許諾契約が成立していたと認められないことは前認定のとおりである。 イ原告は,Aが著作権侵害の事実調査のため,13万2005円を出捐したので,同額分の損害が発生したと主張するが,同損害については立証がなく,認めることができない。 10複製許諾契約に基づく請求(前記第4の2の争点)について(1)本件複製販売許諾契約の成否前記のとおり,被告が,Aに対し,50万円ないし80万円を支払ってきた事実はあるものの,それが定額の複製許諾料の約束に基づくものと認めることはできないのであって,本件プログラムの1セットの複製につき50万円を支払う旨の本件複製販売許諾契約が成立していたと認めることはできない。 なお,別紙1以外の被告による本件プログラムの複製販売で,Aが修正・改造費等の支払を受け,その複製販売を承知していたものについては,個別に複製許諾の合意が成立していた(そして,損害補填の趣旨で,外形的にはライセンス料ともみうる金員が支払われていた)ものと認められるところである。 よって,本件複製販売許諾契約の成立を前提とする同契約に基づく請求は,その余の事項について判断するまでもなく,認めることができない。 (2)原告の主張についてア原告は,50万円ないし80万円の支払は,本件複製許諾販売契約に基づく許諾料の支払であって,損害の填補ではないと主張する。 しかし,前記に認定したとおり,Aは,被告が当初取引の開始を依頼したときに,橘高工学時代の損害の填補を要求し,被告が損害の填補を約束したので取引に応じることにしたのであり,複製許諾の対価として50万円ないし80万円という明確な金額の約束のもとに取引に応じたものと認めることはできない。 イ原告は,金員の授受が許諾料の支払であったことの根拠として,BがAに送信した平成16年5月17日付けメール(乙3)の記載を指摘する。 確かに,同メールには,①「13福丸の件は平成13年3月26日日付で入っている納品書で G1X,LAH 対応ソフト\500,00_,G1X ソフト\800,000_が有りましたね,この中の G1X ソフトが,福丸で別のあまり GPS を使用しない船に13福丸のシステムを移設し,新たなシステムを13福丸に入れたのですその費用を3月26日日付の分で支払っていますので,勘違いをしないで下さい。私の方は裏切ってはいません。」,②「此方は別対応で新たなソフトを構築いたします。」との記載がある。 しかし,①については,原告が被告に宛てた平成16年4月27日付け内容証明郵便(甲7)に対する応答であると考えられるところ,同内容証明郵便では,「無断でのソフト複製権までは許可しておりません。平成13年1月から現在までの申告による請求書送付依頼に基づき弊社が送付した請求内容を下記に示します。…そこで,国土地理院の指導で日本測地系から世界測地系への変更と共に,これに対するソフトの修正を行うにあたり,GPS 処理ソフトにプロテクトをかけました。…これは現在まで2本しか受注しておりません。しかも,このうち1本は貴社が弊社に申告していない福丸建設が含まれております。この事実から,グラブ浚渫ソフトの出荷ごとの支払い契約が守られていないようで,弊社が認知していない出荷先が多々存在しているように思われます」と記載されている。 とすれば,被告としては,福丸建設(13福丸)の件は,被告が原告に申告していないのではなく,ソフト修正費として支払っているという弁解をしているものにすぎない。すなわち,上記記載は,被告においてグラブ浚渫ソフトを自由に複製する権利があるとは考えておらず,第13福丸の件について弁解していることを窺わせる記載であるということはできるかもしれないが,このことから,許諾料を1本50万円とする複製許諾契約が存在することまで認めることはできない。 また,②については,G1X を複製販売しつづけるには,その修正,改造,バージョンアップなど,Aの協力なくして行うことができないことを前提に,新たな別のソフトを開発するから,原告と縁を切っても困らない旨を述べたものにすぎず,許諾料を1本50万円とする複製許諾契約の存在を認定することには足りない。 よって,原告の主張は採用できない。 11本件 GPADver4 開発契約の代金支払拒絶の可否(前記第4の3(1)の争点)(1)被告の主張するバグの内容被告は,本件 GPADver4 開発契約の代金については,本件 GPADver4 ソフトにバグがあり,同ソフトは未完成であるため,代金の支払義務はないと主張し,そのバグの内容は,①本件 GPADver4 ソフトのうち GPADver4 は,世界測地系を選択した場合,基点座標は,別のソフトを用いて変換した日本測地系に基づく座標値を入れないと,偽の座標値が出力されるという不具合がある,②本件GPADver4 ソフトのうち GPADver4.1s は,公共基点Ⅰに対応しないと主張する。 (2)GPADver4 についてア被告の主張するバグの内容は,世界測地系を選択すると偽の座標値が出力されるというものであるが,被告の主張によっても,基点座標に別のソフトを用いて変換した日本測地系に基づく座標値を入れれば,正しく作動するものである。そして,GPAD ver4.0 の基地局の座標入力は,同一工事現場で設定は1度であり,同一工事現場は数か月間続くもので,一度,日本測地系の座標を入力すればシステムは正常に機能するのであり,現に,GPADver4は,既にユーザーに納品され,ユーザーはその状態で GPAD ver4.0 を使用することができている。このように,納品を受けたユーザーにおいて使用可能である以上,これを未完成ということはできない。同ソフトは完成しているというべきである。したがって,被告の主張は理由がない。 イなお,請負契約の目的物に瑕疵がある場合には,注文者は,瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等にかんがみ信義則に反すると認められるときを除き,請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは,報酬全額の支払を拒むことができ,これについて履行遅滞の責任も負わない(最高裁判所平成9年2月14日第三小法廷判決・民集51巻2号337頁参照)。しかし,上記ア認定に係る瑕疵の程度からすれば,被告が報酬の支払を拒むことは信義則に反し,許されないものというべきである。 (3)GPADver4.1s について被告の主張するバグの内容は具体的ではなく,どのような不具合があって,具体的にどのように仕事が未完成で,それが代金拒絶の理由たりえるのかについて,被告は主張立証しない。なお,公共基点Ⅰに対応しないとしても,被告によれば,私有基点,公共基点Ⅱを選択すれば動作するとのことであるから,そうだとすれば,ユーザーは GPADver4.1s を使用することはできるのであって,これを未完成ということはできないこと,及びこれが瑕疵であるとしても報酬の支払を拒むことは信義則に反し許されないことは,GPADver に係る上記認定判断と同様である。 12相殺1の成否(前記第4の3(2)の争点)(1)被告は,Aが本件中国向けソフトを競業他社に納品したことが,契約における信義則上生じる義務違反であると主張し,同債務不履行に基づく損害賠償債権を自働債権として相殺の抗弁を主張しているところ,原告は,本件斜杭打設管理ソフトの著作権がAに帰属すると主張して,Aの販売禁止義務を争っている。 仮に,Aに販売禁止義務があったとしても,相殺は,同一当事者間において双方が互いに同種の目的を有する債権を負担する場合に,対当額についてその各債務を免れることができるとするものであるから,Aの債務不履行による被告のAに対する損害賠償債権を自働債権として,原告の被告に対する代金債権と相殺することができると主張する根拠は不明である(被告は,原告はAが法人なりしたものであると述べるにすぎない。)が,その点はさておいて,Aに本件斜杭打設管理ソフトの著作権が帰属するかどうかについて判断する。 (2)証拠(各事実の末尾に記載)等によれば,次の事実が認められる(争いのない事実,既に認定済みの事実も含む)。 アAは,平成3年9月ころ又は平成4年2月ころ,橘高工学から依頼を受けて,本件斜杭打設管理ソフト(甲26〔IPT.C,平成4年2月〕又は乙20〔SCS_COM.C,平成3年9月〕はそのソースプログラム〔いずれが本件の斜杭打打設システムのソフトであるかは不明〕,甲27は甲26の画面のハードコピー。)を完成させた。 イ本件斜杭打設管理ソフトのソースプログラムには,橘高工学の名前が記載されているが,「(c)Copyright」等の付された著作権表示は,Aのものも橘高工学のものもいずれもない(甲26,27,乙20)。 ウ本件斜杭打設管理ソフトの開発にあたり,橘高工学は,センサーなどの機器構成図を示したのみで,具体的な指示をすることなく開発をAに一任し,3次元空間における杭打ち演算のロジックはAが考案した。 エAは,平成3年ころから平成4年ころは,月100万円の固定報酬で,橘高工学の受注プログラムの開発に専従していた。 オ本件斜杭打設管理ソフトはプログラムの著作物である。 (3)以上の事実を前提とすれば,本件斜杭打設管理ソフトは,Aが独自に創作したもので,その著作権を橘高工学に譲渡する旨の明示の合意はなく,Aは,他のプログラム開発も併せた月100万円の固定報酬は,プログラム開発費として受領したものの,著作権の譲渡の対価に相当する額の金員の受領はなく,特に橘高工学の著作権表示を付しているものでもないから,その著作権はAに帰属する。 したがって,Aは,本件斜杭打設管理ソフトについて,その著作権に基づき,自由に複製したり,その複製物を販売することができる。 (4)被告は,本件斜杭打設ソフト変更契約により,注文者である被告は,当然その成果物及び提供した情報を注文者の利益のために用いることを予定して競業他社に類似するソフトの販売を禁止していたし,Aも,契約書に明文がなくても,被告に無断で競業他社に類似するソフトを販売しないという信義則上の不作為義務を負ったと主張する。 しかし,前記のとおり,Aは,本件斜杭打設管理ソフトの著作権者であるから,被告は,Aから許諾を受けて,本件斜杭打設管理ソフトを複製,改変できるものにすぎず,Aは,被告から依頼を受けて,同ソフトのプログラム言語やOSを変更する作業をしたからといって,その著作権の行使を制約されることはない。また,被告は,本件斜杭打設ソフト変更契約に際し,被告が提供した情報をAが無断使用したかのような主張をするが,そもそも本件斜杭打設管理ソフトは,Aが著作権を有するプログラムであって,仮に被告から何らかの情報の提供があったとしても,そのことで直ちに著作権の行使が制約されるものではない。そして,被告は,その他に,被告が提供しAが無断使用したとする情報内容について主張立証しない。 したがって,本件斜杭打設管理ソフト変更契約により,同ソフトの著作権者であるAが,被告が主張するような不作為義務を負うことはないのであって,被告の主張は失当である。 (5)以上より,Aないし原告に,本件斜杭打設管理ソフト変更契約の債務不履行に基づく損害賠償債務は発生しないので,同損害賠償債権の存在を前提とする被告の相殺の抗弁は認められない。 13相殺2の成否(前記第4の3(3)の争点)(1)被告は,原告の本件送付文書の送付が不正競争防止法2条1項14号に該当する行為であることを前提として,同法4条に基づく損害賠償請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張するので,原告の本件送付文書の送付が,同法2条1項14号の不正競争行為に該当するかどうかについて,まず判断する。 (2)証拠等(各事実の末尾に記載)等によれば,次の事実が認められる(争いのない事実,既に認定済みの事実も含む)。 ア乙5文書には,「日頃は,弊社製のグラブ浚渫ソフトをご利用頂きまして,厚く御礼申し上げます。」「…御社様の採用されて居られます,弊社製のソフトの使用状況及び,問題点その他なんでもご遠慮なく御聞かせ頂ければと,今回手紙を送付させて頂いた次第で御座います。」との記載があり,同文書の本文の別紙の「お客様ご回答用紙」には,「浚渫ソフト名」欄に「(1)G1W(2)G1X (3)他」の記載があり,「GPS ソフト名」欄に「(1)RTPS (2)GPAD (3)他」の記載がある(乙5)。 イ乙6文書には,次の記載がある(乙6)。 「先日は,ご多忙中突然のアンケートを御願い致しまして誠に申し訳なく思って居ります。しかしながら,こちらのアンケート依頼に対して,ケルシステム社より,何らかの干渉があった様ですが,再度,御社様へのアンケートを御願いさせて頂かなければならない事をどうぞ御許し下さい。」「これまで,御承知の通り弊社は,開発したソフトをケルシステム社や他社へ納入販売してきましたが,この度,販売報告のない出荷が,ケルシステム社において発生して居ります。この書面上で,詳しい事は申せませんが,著作権に関する,しかるべき手続きをとる上で,直接弊社と御取引のないケルシステム社の顧客様で有られます御社様には,御迷惑を御掛けしない為に,なにとぞご理解,御協力頂けます様,再度,御願い申し上げる次第で御座います。」ウG1X MS-DOS 版及び本件プログラムの著作権はAが帰属していたが,譲渡により現在は原告に帰属していることは前示のとおりである。 エGPAD は,G1X シリーズの GPS 処理のためのプログラムをいうものと解されるところ,同プログラムは,入力部分,演算部分,出力部分に分けられ,うち演算部分の著作権は,WayPoint 社に帰属する。また,RTPS のプログラムの一部も,著作権が WayPoint 社に帰属する。RTPS,GPAD は,WayPoint 社のプログラムにAが手を加えて作成したものである(甲10,弁論の全趣旨・被告の平成19年4月19日付け第19準備書面18ページ)。もっとも,Aが新たな創作性を付加したとの立証はないため,これが二次的著作物であるとか,その著作権が原告に帰属するということはできない。 (3)乙5文書について被告は,乙5文書で「弊社製」という文言が用いられている部分が虚偽であると主張する。 前記認定のとおり,確かに,乙5文書には「弊社製」という文言があり,乙5文書の本文の別紙の「お客様ご回答用紙」には,アンケートに回答する顧客が使用しているソフト名を記入するために,G1W,G1X,その他の浚渫ソフト,RTPS,GPAD,その他の GPS ソフトの名称を記入する欄が設けられている。 しかしながら,「弊社製」ソフトの意味は,必ずしも「原告が法的な意味での著作権を有するソフト」という意味にしか理解できないわけではなく,「原告が労力をかけて製造して(それが複製なのか翻案なのか,全く新しい著作物なのかという法的問題はさておき)販売している,あるいは販売先に卸しているソフト」の意味とも理解することができる。この意味では,G1W,G1X,RTPS,GPAD はAないし原告製造ということができる。 また,乙5文書は,「弊社製ソフトの使用状況及び,問題点」等を聞かせてほしいと述べるものであって,G1W,G1X,その他の浚渫ソフト,RTPS,GPAD,その他の GPS ソフトのすべてについて「弊社製」であると断言しているものではない。 したがって,乙5文書の「弊社製」の記載が「虚偽の事実」であるとまでいえない。 (4)乙6文書について被告は,本件送付文書をみれば,原告が著作権を有する「グラブ浚渫ソフト」あるいは G1W,G1X,RTPS,GPAD について,被告が原告の許諾を得ることなく,あるいは許諾の範囲を超えて複製しているかの印象を与えると主張する。 前記認定のとおり,乙6文書には,直接ソフトの名称は記載されていないが,「先日は,ご多忙中突然のアンケートを御願い致しまして誠に申し訳なく思って居ります。しかしながら,こちらのアンケート依頼に対して,ケルシステム社より,何らかの干渉があった様ですが,再度,御社様へのアンケートを御願いさせて頂かなければならない事をどうぞ御許し下さい。」と記載されていることから,本件送付文書を併せて読めば,乙6文書においては,乙5文書で列挙されたソフトである「グラブ浚渫ソフト」あるいは G1W,G1X,RTPS,GPADについて言及されていることが理解できる。 そして,前記認定のとおり,乙6文書には,「これまで,御承知の通り弊社は,開発したソフトをケルシステム社や他社へ納入販売してきましたが,この度,販売報告のない出荷が,ケルシステム社において発生して居ります。この書面上で,詳しい事は申せませんが,著作権に関する,しかるべき手続きをとる上で,直接弊社と御取引のないケルシステム社の顧客様で有られます御社様には,御迷惑を御掛けしない為に,なにとぞご理解,御協力頂けます様,再度,御願い申し上げる次第で御座います。」と記載があることから,原告が開発したソフトを被告に納品してきたこと,同ソフトについては原告に著作権があり,被告は原告に対して,許諾を受けて販売しているソフト数について報告義務があるにもかかわらずこれを怠っていることを事実として指摘していると読むことができる。 しかしながら,乙6文書は,「開発したソフト」として直接ソフトの名称を列記していないことから,乙5文書の別紙に列挙されている「グラブ浚渫ソフト」あるいは G1W,G1X,RTPS,GPAD のすべてについて,原告が開発して著作権を有し,被告が許諾を受けて販売しているソフト数について報告義務があるにもかかわらずこれを怠っているとまで読むことはできない。そして,前記認定のとおり,少なくとも,G1X MS-DOS 版及び本件プログラムについては,原告は,著作権を有しており,「G1X」については,被告は,原告の許諾を受けず,これを販売して,原告の著作権を侵害した事実がある(なお,被告は原告の許諾を受けて販売していたものもあることから,そのような方法をとることも可能であったという意味において,報告を怠っていたということもできる。)。 したがって,乙6文書に記載された事実も「虚偽の事実」であるとまでいうことはできない。 (5)よって,本件送付文書は,いずれも「虚偽の事実」が記載されたものであるということはできないから,これを被告の取引先に送付することは,不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為に該当しない。 したがって,同号の不正競争行為があったことを前提とする損害賠償債権を自働債権とする被告の相殺の抗弁は理由がない。 14結論以上の次第で,(1)G1X MS-DOS 版は,少なくとも位置決めプログラムを原著作物とする二次的著作物であり(前記3),その著作権は著作者であるAから譲渡を受けた原告に帰属している(同4)。本件プログラムは,G1X MS-DOS 版の二次的著作物であり(同5),その著作権は著作者であるAから譲渡を受けた原告に帰属している(同6)。したがって,原告は,本件プログラムについて,二次的著作物の著作権者の立場と,その原著作物に当たる G1X MS-DOS 版の著作権者の立場の両面で,本件プログラムについて著作権を有している。 よって,主位的請求たる原告の本件プログラムの著作権に基づく差止請求は理由がある。 (2)本件プログラムの複製販売を理由とする金銭請求は,ア主位的請求であるプログラムの著作権侵害に基づく損害賠償請求は,700万円(1複製35万円で20回分)及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は(著作権侵害の事実調査費用相当損害も含めて)理由がない(前記9)。 イ予備的請求である複製販売許諾契約に基づく請求は理由がない(同10)。 (3)ソフト開発ないし改造等の請負契約に基づく代金及びこれに対する遅延損害金の請求は理由がある(前記11)。被告の相殺の抗弁はいずれも理由がない(同12,13)。 よって,原告の請求を主文第1ないし第3項の限度で認容し,その余は棄却することとして,主文のとおり判決する。 |
| 裁判長裁判官 | 山田知司 |
|---|---|
| 裁判官 | 高松宏之 |
| 裁判官 | 村上誠子 |